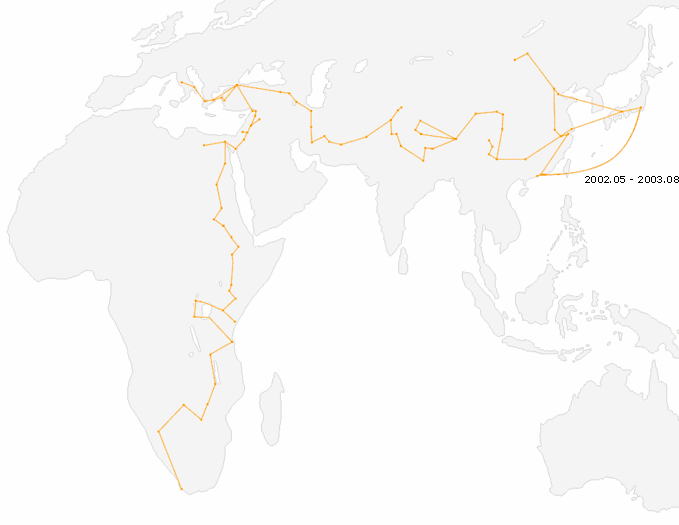ラサを出てから、2日かけてラツェという街まではバスで行ったが、そこから西チベットは旅して、ネパールに抜けるまでの移動は、全てトラックのヒッチハイクだった。
数えてみると10台のトラックをヒッチしたことになる。
西チベットを、トラックをヒッチして移動することは、決して楽なものでなかったが、ヒッチでしかできないような体験も多かったし、出会えない風景も多かったように思う。
トラックの乗り心地と、移動のスピードは、道の状態もさる事ながら、ドライバーの性格とやる気によるところが大きい。
いろいろなドライバーがいて、いろいろなトラックに乗った。
幌がなく、土埃がひどくて、眉毛に砂がつもって仙人のようになったトラック。
実際には2泊3日の距離なのに、寄り道が多く、いつ聞いても「明日着く」と言って結局4泊5日かかったトラック。
家に招いてくれて、インスタントラーメンや、ご飯をごちそうしてくれたドライバー。
宴会が始まってひたすらワインみたいな酒をすすめられて、気持ち悪くなるまで飲まされたこともあった。
なかでも最悪のトラックはツァンダからタルチェンまでのトラックだった。
そのトラックのことは忘れたくとも忘れられない。
ツァンダでそのトラックを捕まえたのは早朝で、最初の値段交渉はスムーズだった。
料金を紙に書いてドライバーに確認して、荷台に上ってみると、すでに数人のチベット人と日本人が乗っていた。
トラックの振動は、荷台のなかでも場所によってだいぶ違うということを、今までの経験で学んでいたから、なるべく振動の少ない前の方に行きたかったが、いい場所にはすでにチベタンがいた。
さらにその後方に数人の日本人がいた。
必然的に空いているスペースは荷台の一番後ろしかなく仕方なくそこに座った。
トラックの荷台の床は固い。
ただの鉄板だ。
チベタンは用意周到に敷物を持っているし、先客の日本人は、チベタンの野宿用の分厚いマットを借りてクッションにしていたが、私が借りる分はもうない。
私は何か敷くもの探したが見当たらなくて、トラックの振動がちょっと心配だった。
そして走り出したそのトラックは、この世の中で最も乗り心地の悪い乗り物だと断言してもいいくらいひどいものだった。
道は山道が続きでこぼこで、ドライバーは荷台に人が乗っていることなんかおかまいなしに、ぶっ飛ばすものだから、そのでこぼこの度に振動が荷台を突き上げる。
ガタンという度に体全体が宙に浮いて、着地の時に尻の骨を打つ。
尻の痛さも耐え難いものだったが、その衝撃が内臓に伝わりそれもきつい。
まるで空手で中段突きを食らった時のような感覚だ
必死にトラックのふちにしがみついても、まるで意味がない。
自分の着替えを敷物にしたがほとんど効果がない。
おまけに、荷台にくくりつけられたバカでかい予備タイヤが、ロープで縛ってあるはずなのに、何十センチもバウンドして何回も足をはさみそうになる。
それは乗り物とはいえない。
何かの罰ゲーム、いや何かの刑罰となり得るものだ。
途中、何回も「もう降りよう」と思ったが、他のトラックがいつ捕まるかわからない
で必死にこらえた。
戦いは12時間続いた。
タルチェンに着いた時にはヘロヘロに疲れていた。
宿で荷物をチェックしてみると、ガソリンコンロの鉄の部分が振動で曲がっていた。
しかし悪い体験ばかりではない。
ヒッチを始めたラツェという街はずれの、ダプという村では、2日間トラックを待ったが、村人たちがとても親切にしてくれた。
水をくれたりバター茶をごちそうしてくれたり、家に招いて三味線のような民族楽器を披露してくれたりした。
村の子供たちもたくさん集まってきて、写真を撮らせてくれたりもした。
彼らとはトラックを待つ間、日本の遊びを教えて一緒に遊んだりした。
別れ際、子供たちが口々に「1元ちょうだい」と言ってきたのには少しがっかりしたが、そんな中「そんな事いうな」と言って、彼らを諭している年長の少年がいた。
その少年の眼差しは他の誰よりも凛としていた。
そのダプから乗ったトラックは、最初馬鹿みたいな料金を言ってきて、値切るのにてこずったが、いざ乗ってみるとなかなか快適なものだった。
ドライバーの二人も優しい人たちだった。
荷台にはパイプが山積みになっていて、他に乗っている人もいないので、その上で横になれた。
荷物に気を使って走るドライバーだったので、振動も少ない。
幌付きのトラックで晴れると前の部分を開けてくれて、景色を楽しめたし、ちょっとした雨でもわざわざ幌を閉めてくれた。
夜はドライバーと一緒にその荷台で寝かせてもらったから、宿代もかからなかった。
彼らは休憩の度にバター茶をご馳走してくれた。
最初はやはりおいしいとは思えなかったが、慣れてしまえば案外いける。
ある時、そのバター茶を飲みながら、地図を広げどの辺りまで進んだのかをドライバーと話していた。
草原にぺたりと座って、あと何日かかるとか、そんか会話をしていた。
その地図には「西蔵自治区地図」と書かれてあり、私がラサで購入したものだった。
彼らは「自治区」の部分を指で隠し、「これが本当の呼び方だ」とでも言っているようだった。
ここに住む人たち、景色、文化、どれ一つとっても中国ではない。
旅行者の私などはここが中国だなんてことは忘れていた。
ここはチベットだ。
やはり一つの国なんだ。
私も「自治区」のところを指で隠し、ちょっと笑いながら「今どこにいる?」と聞いてみると、彼らの顔もまた微笑んでいた。