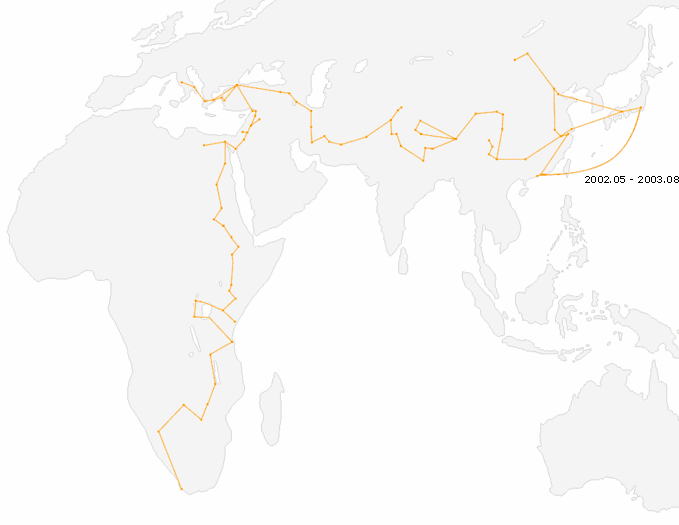ラフィーリアというその病院は、思ったよりも清潔で近代的だった。
5階だてくらいの白い建物で、入り口には救急車が数台止まっている。
受け付けに行く途中には、何種類ものポスターが張ってあった。
そのほとんどが、銃をもったパレスチナの男たちだ。
その男たちは、イスラエルと戦って死んでいった者たちらしい。
彼等は西側諸国から見ればテロリストかもしれない。
しかし、ここでは英雄なのだ。
そのラフィーリア病院は、ウエストバンクのナブルスという街にあった。
そこへ行くには、エルサレムから乗合タクシーでカランティアというところまで行く。
そこには、何もないが、ウエストバンクの街へ行く分岐点で、タクシーが集まっている。
さらに乗合タクシーを乗換え、カランティアから次にフアラというチェックポイントまで行く。
そこまでは田舎道が続き2時間かかった。
途中、紫と黄色の名前は知らない花が咲き乱れていた。
ここにだって春はやってくる。
チェックポイントの手前で乗合タクシーを降ろされ、そこから5分ほど歩くと、チェックポイントがあった。
そこをタクシーで通過できないので、チェックポイントを徒歩で通過して、タクシーを乗り換えなければならない。
そこでは多くのパレスチナ人が列をつくっていた。
イスラエル兵が、一人一人のIDカードと、荷物をチェックしているので、相当時間がかかりそうだった。
私たちも彼等と同じように列に並ぶ。
この日、ラフィーリア病院へと行ったのは、私とKさんだった。
Kさんはヘブロンへ一緒に行ったうちの一人だ。
彼はまだ19歳だったが、英語がうまく、心強かった。
驚いたことに、その行列のなかで、コーヒーとお菓子を売っているパレスチナ人がいた。
ポットにコーヒーを入れ、箱にお菓子を入れ、売り歩いているのだ。
そして、けっこう繁盛している。
私もコーヒーを買って、そこでKさんと待っていると、
『外国人は横から入れる』
と、パレスチナ人が教えてくれた。
しかし、列の横から出て、前のほうへ行ってみたはいいが、どうしたものかと思っていると、チェックポストのイスラエル兵に呼ばれた。
もちろん彼等は武装している。
パスポートを提示し、ナブルスへ行く理由を聞かれ、
『友達に会いに行きます』
と適当な理由を言った。
ウエストバンクへ観光へ行くとは言えなかった。
それだけ、緊張している地域なのだ。
それで、検問は通過出来た。
そこからまた乗合タクシーで、ナブルスの中心まで行き、そこでタクシーをチャーターして、目的のラフィーリア病院まで来るができた。
まずは受け付けで、病院見学の目的を話した。
それは、私がフリーのカメラマンで、Kさんがその通訳という設定だった。
そして、パレスチナに関するレポートをつくっているので、見学させてほしいと言った。
その病院には、イスラエル兵の犠牲となったパレスチナ人が運び込まれてくる。
私たちは彼等に会い、話を聴いて、写真を撮るために来たのが本当の理由だ。
しかし何の肩書きもなく、NGOでもない私たちが、
『旅行者です』
とはやはり言えずに、そういう設定を考えていたのだった。
受け付けで、病院長の部屋に案内され、まずはその病院長と話をした。
『私はフリーのカメラマンで、パレスチナに関するレポート作成しています。
日本の報道はアメリカ、つまりはイスラエルに寄っていてる。
だから本当のことを知りたいのです』
と、Kさんが切り出した。
カメラマンであることと、レポートを作成していること除けば、それは間違ってはいない。
病院長は、私たちの申し出を快く引き受けてくれた。
私たちは、他の医師の案内で、入院患者の部屋へと案内された。
数人の青年がベッドによこたわり、一人は左足に弾を受け、貫通したと言っていた。
他には5、6発の銃弾を受けた青年もいた。
話をきくといずれも家にいて、イスラエル兵が侵入してきて撃たれたと話していた。
そして、その後、集中治療室と書かれた部屋に通された。
顔が変形するほど殴られた青年がいた。
昨日、他の村へ行こうとして、入植者、つまりユダヤ人になぐられたのだ。
銃のつかで殴られたらしい。
その父親に、
『こんなことは、ここではめずらしくないんだ。日本政府は何も知らないだろう』
と言われた。
また14歳くらいの少女が横たわっていた。
3日前に、ジェニン(同じくウエストバンクにある街)にある家の前で遊んでいたところ、イスラエル兵に撃たれた。
その銃弾が左目から入り、まだ脳のなかにあるという。
脳が損傷し、自力での呼吸ができずに、のどから人工呼吸器を入れていた。
意識はない。
話をしてくれて医師は、
『明日もっと大きな病院に移すが、きっともうだめだろう』
と話していた。
15歳の少年もいた。
家になかに突然イスラエル兵が入ってきて、父親に逃げろと言われたが、逃げ遅れ、頭を撃たれた。
撃たれたのは2週間前だ。
彼も呼吸ができずに、喉を切開して、そこから管を通していた。
言葉なく、意識があるかはわからないと医師は話していた。
彼の兄が彼の耳になにかをつけていたので、よく見ると、それはウォークマンだった。
『以前、よく聴いていた歌だから・・・』
と静かに話していた。
カメラを向けると彼の眼が私を向いた。
それが意識的なものなのか、ただの反射的なものかのかはわからない。
彼等は、一般の武器も持たない市民だった。
それも幼い。
そして、理由もなく撃たれた。
この国は戦争をしている。
いや戦争が国と国、あるいは軍隊と軍隊との交戦を意味するのであれば、ここでの状況を戦争とは呼べないかもしれない。
それはあまりに一方的な戦闘だ。
私は彼等を写真に収めた。
私はシャッターを切りながら思った。
私が今撮っているものは、今まで撮ってきたものとは全く違う。
『彼等を撮って一体何になるのだろう』
と、自分に問う。
私は本当のことを知りたいからと言って、ここへ来た。
そして彼らはより多くの人に真実を伝えて欲しいと願っている。
しかし、私はただの旅行者だった。
ただ、他の旅行者よりは少しばかり大きなカメラを持った、ただの旅行者だった。
最後に再び病院長に会い、礼を述べ、また話しを聞いた。
『この病院だけでインディファーダ(投石などによるパレスチナの抵抗運動)が始まってから、4500人が怪我して運び込まれ、そのうち400人が死んだ。
正確な数は正直よくわからない。
救急車でさえ、撃たれることもあるし、検問を通れないこともある。
それで、患者が死ぬことだって、めずらしくない。
私の祖父も、テルアビブに住んでいたが、奴等に追い出された。
そして、今は、このナブルスにさえ、奴等はやってきた』
私たちは自爆テロについて思いきって聞いてみた。
『家族を殺されたから自爆テロをするんだ。
パレスチナには軍隊も武器もないからそれしかない。
しかし、テロについては、パレスチナの9割の人が賛成していない。
テロでユダヤを一人殺せば、報復に100人は殺される。
でもテロを止めろとは言えない。
家族を殺されたんだぞ。
他の国は、本当のことを何もしらない。
日本だってそうだ。
なぜ、アメリカの肩を持つんだ』
私は言葉を返せなかった。
本当に私がフリーのフォトグラファーだったらよかったのに。
そうすれば、少しは彼らの気持ちを代弁できるのに。
私はそう何度も思った。
ラフィーリアの病院を後にして、私とKさんはタクシーで、ダウンタウンへ行き、そこをあてもなく歩いた。
ダウンタウンのス?クは、商店が普通に開いていて活気もあった。
そしてメインロードにぽつんと一軒崩壊して家があった。
それをボンヤリと見ていると、
『一ヶ月前にイスラエルにやられたんだ』
と通りがかったパレスチナ人が教えてくれた。
私はたちがさらに奥へと歩いていると、ある老人が家の軒先から話し掛けてきた。
彼は全く英語を話さないが、どうやら家のなかに入れと言っている。
とにかく入ってみると、壁に大きな穴があいていて、その下には壊された石の壁の破片が散乱している。
爆破されて穴が開けられたらしい。
『見てくれ、全てイスラエルの奴等がやったんだ』
とでも老人は言っているようだった。
その穴の向こう側を覗くと、今度は青年が立っていた。
それはその青年の家だった。
壁に穴があいたので、老人と青年の家が繋がってしまったのだった。
少し英語のできる彼は、
『カム、カム』
と言っている。
彼について、彼の家を通らせてもらうと、また大穴があいている。
それを覗くと、今度は女性ばからりの家族が食卓を囲んでいた。
さすがに女性しかいないので、その家に行かせてもらうのは、はばかられたので、挨拶して退散することにした。
すると今度はその彼が、
『まだこっちにもある』
と言って案内してくれ、また別の家に大穴で続いていた。
そして、その家の婦人がチャイを振る舞ってくれた。
彼女は英語は話さないが、歓迎してくれているのが伝わってきた。
つまりは彼等は知ってほしいのだ。
本当にここで起こっていることを。
大穴を開けるのはイスラエル兵である。
彼等は夜、街に侵攻し、家を破壊したり、家の壁を爆破しそこを通過する。
時にパレスチナ人を撃つ。
イスラエル政府が「テロ対策」と称しているそれに、一体どんな意味があるのかは私には理解できなかった。
テロ対策とは、単なる名目にしか思えない。
そして、パレスチナが自爆テロをやると、その出身者の街を破壊しに行く。
その、穴をつたっていった最後の家でチャイを飲みおわると、私たちは帰ることにした。
それにしても、深夜寝ているときに、突然軍隊が自分の家にやってきて、爆弾で穴をあけ、そして中を我が物顔で家の中を通り、銃を向けられ、時に撃たれるというその恐怖は、いったいどういうものだろうか。
それはいくら想像してみても、きっと真実にはたどりつけないだろうと思った。
きっと、体験しないとその恐怖はわからない。
夜、宿に戻ると、客の誰もが無口だった。
その理由を他の旅行者が教えてくれた。
ISMというNGO団体の一員であった、アメリカ人の女性が殺されたのだ。
彼女は、このホテルもよく利用していたので、オーナーをはじめ、直接彼女を知っている人も多かった。
ISMの活動内容は、いわばヒューマンシールドである。
パレスチナの生徒が小学校へ行くのについていったり、あるいは、パレスチナの家に住み込んで、イスラエルが家を破壊するのを止めたりする。
イスラエルはさすがに外国人には、簡単に手を出さない。
だから、要は、ISMはパレスチナ人と一緒に行動することで、彼等を守っているのだ。
その女性は、イスラエルの侵攻が激しいガザで殺された。
そのラッファという街では、次々に家が壊され、パレスチナ人が殺されているらしい。
彼女はそこで活動していた。
イスラエルのブルドーザーが、パレスチナの家を破壊しようとしていたときだったらしい。
彼女はいつもと同じように、その前方に立って、手を振って止まるように合図を送った。
いつもなら、止まっていた。
しかし、その日の、そのブルドーザーは止まらなかった。
ブルドーザーは止まることなく、彼女の目の前へと進んできた。
危険を感じた彼女は、ブルドーザーを止めることを諦め、逃げ出した。
しかし、彼女はつまづいてしまった。
そこにブルドーザーは彼女の上から土砂を被せ、そして、その上を通過して轢いた。
さらにバックして、もう1回轢いたのだ。
彼女はまだ23歳だった。
私は、それまでガザに行くかどうか迷っていた。
しかし、その話しを聞いて止めることにした。
それは危険があるからという理由もある。
それ以上に、旅行者という立場で、それ以上深入りするのが嫌だったからだった。
いや同時に行きたいという気持ちも強かった。
正確にいえば、行くからには何かをしたいと思った。
具体的には、そのISMの活動を手伝うことも難しくはない。
しかし私は旅人であることを優先した。
しかし、私はここへ来たことを後悔はしていなかった。
フォトグラファーだと言って、病院へ行ったことも、多少の罪悪感はあるが、後悔はない。
知らないよりは、知った方がいい。
私はそう思っている。
事実、ここへ来るまでは何も知らなかったと言っていい。
自爆テロのことをニュースや、新聞で読んでもよくわからなかった。
それは単にイスラム教の教えに関係しているのかもしれないと思っていたくらいだ。
何でそこまで駆り立てられるのかが、わからなかったし、正直それ以上の興味がなかった。
しかここへ来て、それに駆り立てるものがわかった。
家族を殺されたからである。
それも、そのほとんが理由もなくである。
それは、報復をするのに、十分で単純で、もっとも説得力ある理由だ。
そして、報復が報復を生んで、また繰り返される。
別にパレスチナに正義があって、ユダヤには全くそれがないかどうかは、私にはわからない。
ユダヤ人が一方的にパレスチナに侵攻していると私は感じたが、パレスチナ人もテロでユダヤ人を殺している。
取り残された家族の無念さというのは、人種を問わないはずだ。
それに私にはどちらが正しいと言えるほどの知識がないしその歴史も知らない。
第一、その国の薄皮一枚しか見ていない旅行者がそれを口にすることに、抵抗を感じる。
それでも私は思う。
本当に私がフォトグラファーだったら良かったのにと・・・