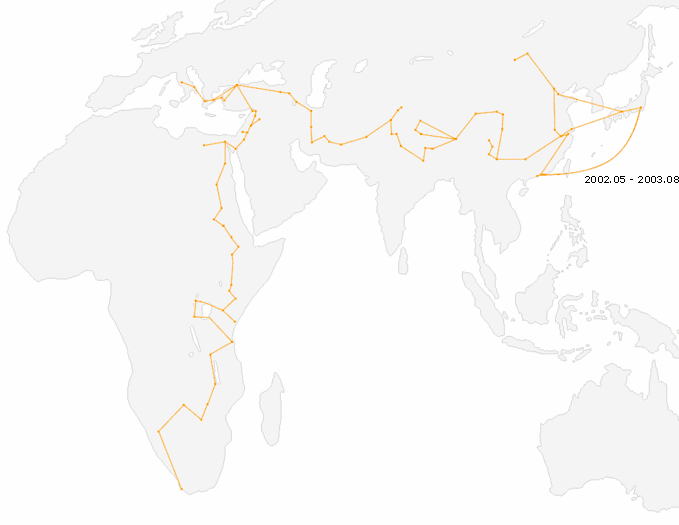年が明けた。
といっても除夜の鐘が聞こえるわけでも、カウントダウンをしたわけでも、花火が上がったわけでもない。
ここイランでは西洋暦の新年を祝う習慣はない。
私はただ時計を見てそれを確認しただけだった。
あまりに普通すぎる2003年のスタートだった。
私は元旦から移動をした。
ここ、バムにいても、もうやることがなかったからだ。
私はケルマンという小さな街へ行った。
その街は伝統的なチャイ屋とバザール以外特に見るものがなかった。
そこで1泊しようと思ったが、安宿がどこもいっぱいだった。
もしかしたら外国人だから断られたのかもしれない。
イランの小さな宿は、外国人を嫌う風潮がある。
中級ホテルは空いていたが、余分な金は使えないので、結局そこには泊らず、夜行バスでシラーズへと向かった。
そこはぺルセポリスという有名な遺跡の観光の拠点となる街だった。
ペルセポリスは世界史の教科書にも写真が載っているくらい有名だ。
イランに来たからにはと思って、私もそれを見学した。
レリーフなどの価値は確かにすごいものだと思えたが、正直私にはその価値がわからない。
こんなとき、受験の時に、日本史ではなく世界史を勉強しておけばよかったとだった
とつくづく思う。
私は過去の死んでしまった人や、物よりも、現在も生きているものに惹かれるのだなと思った。
だからチベットのラサや、インドのバラナシでは何日いても飽きることがなかったのだ。
あそこは今でも、街そのものが生きているような気がした。
私はきっと、たとえ歴史に詳しくても過去に思いをはせるのは数分で飽きてしまうだ
ろうが、脈々と生きつづける街や、人間のありさまには飽きることがないと思った。
別にどっちが正しいとか間違っているとかいうのではなく、私はそういうタイプの人間なのだと思う。
シラーズでは、ほかにシャー・チェラーグ廟というところに行った。
そこはここで殉教した、セイエド・ミールアフマドという人の棺がある。
その棺が安置されているドームに入ると、内側の壁は細かい鏡が無数にはめ込まれていた。
何十人ものイラン人の巡礼者がその棺の前で立ち止まり、棺の周りの柵に接吻している。
なかには泣き崩れている人もいた。
そのセイエド・ミールアフマドという人がどんな人かは全くわからないが、ここは聖地であることを感じた。
とにかくシラーズで見るべきものは見て、エスファハンに向かった。
そこは日本でいえば京都のような所らしい。
かつては「世界の半分」とうたわれたほど栄えたらしいが、現在見ても正直な印象は「そこまで言うか?」という感じだった。
実際そういう時代もあったのだろうが、今はただの観光地だ。
しかしモスクのタイルの装飾などは、極めて細かく美しくと思ったが、それだけだった。
そして私はテヘランへやってきた。
イランに入ってからまだ10日も経っていない。
我ながら急ぎ足だ。
というより、腰を落ち着けたくなるような街がないから、次へ次へと進んでいると言ったほうが正しいかもしれない。
テヘランへは夜行列車で到着し、地下鉄に乗り換え中心街へとやってくると、ずいぶんと都会を感じた。
ビルが並び、車も多く、排気ガスもひどい。
テヘランのゲストハウスでは、ある日本人がトラブルに遭ったと言っていた。
夜行バスで盗難に遭って、持ち金のほとんどを奪われ、日本に帰るはめになり、宿でパスポートの再発行を待ると話していた。
また情報ノートにはナイフ強盗に遭って、抵抗して手を切られた話しが書いてあった。
それはわずか1ヶ月前のことだった。
他にも、石を投げられたり、卑猥な言葉でからかわれたという話しもイランに入ってから何度も聞いた。
とにかくイランではトラブルが多い。
そんなイラン人はごく一部で、そんな輩のせいで、
『イラン人は最低だ。悪い奴が多い』
なんて言うのはバカげていることはわかっている。
しかも私自身は何も被害にあっていないし、嫌な思いをしたことさえない。
それどころか、バムでは忘れられない親切を受けた。
にもかかわらず、私自身もイランには長くいたくないというふうに思い始めていた。
イランは、中年からそれ以上の人たちは、限りなく親切である。
それにバブルの頃はイランから日本へ出稼ぎに行った人も多く、中年のおじさんたちのなかには、突然日本語で話し掛けてくれる人もいる。
彼らはみんな親日家だった。
しかし、若者たちには、どことなく歓迎されていないような気がした。
バスターミナルなどでバスを待っていると、20歳くらいの若者たちが私を見てニヤニヤしているなんとことはよくあった。
なんとなくバカにされている気分になる。
それは反米感情が反日感情にも結びついているのかもしれない。
次の日、地下鉄に乗って、旧アメリカ大使館へ行ってみた
1979年のアメリカ大使館人質事件の現場だ。
今は専門学校になっていて中には入れない。
外側の壁には骸骨の顔をした自由の女神や、アメリカの国旗の模様をした手が、ペルシャ絨毯に火をつけようとしている絵が描かれてあった。
俗っぽく言えば「ファッキン・アメリカ」の絵である。
門の所に警備員がいて、写真を撮っていいかどうか聞くと、意外にもOKの返事だった。
そんなもん撮ってもしょうがないと思いつつ、数回シャッターを切った。
その近くにナショナル・フォトギャラリーというのがあり、ちょっと覗いてみた。
誰の作品かはわからなかったが、50点ほどの白黒の写真が展示してあった。
イランの地方の風景や人物の写真だった。
テヘランで見たものはその二つだけだった。
私はその日のうちに荷物をまとめ宿を出た。
テヘランには1泊しかしていない。
駅へと向かった。
チケットはもっていなかったが、なんとかなるだろうと思っていた。
夜行列車はいっぱいだと言われ、キャンセル待ちの客たちが30人ほどいた。
私も彼らと一緒に待っていたが、係員は何故か一番最初に、私にキャンセルチケットをまわしてくれたようだった。
私はさらに西へと移動することになった。
別にこの国を嫌いではなかったし、いまでもそうだ。
しかし妙な居心地の悪さというやつはあった。
単に相性が悪かったのかもしれない。
だからイランには2週間も滞在していない。
早く西へと行きたいというよりは、その妙な居心地の悪さが、一つの街に腰を落ち着けることを許さず、結果的に早足でここまで来て、さらに先を急いでいる。
次はトルコ。
アジアの終着駅だ。