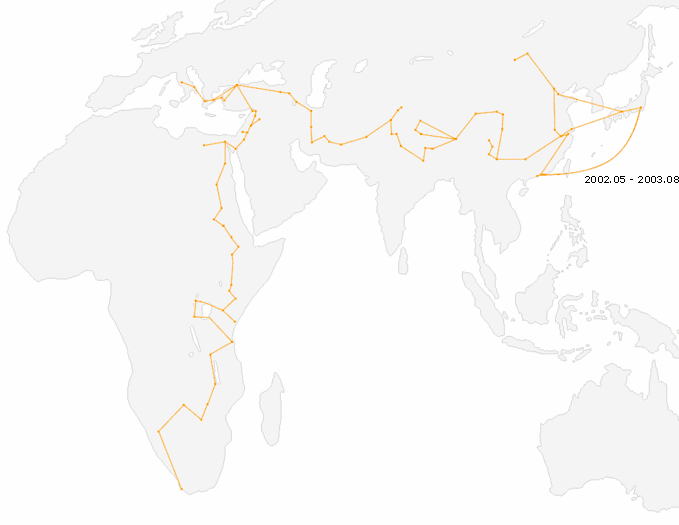そこまでの道のりは、文字どおり険しかった。
ウランバートルからのバスは10人乗りのワゴン車で、そこに13人くらいを押し込み走り出す。
老人などは助手席でゆったりと座れるが、私を含めそれ以外の人は、狭い座席に肩と肩、膝と膝を寄せ合って、身体を斜めにしないとシートに座れないくらいのスペースしかない。
おまけに、その膝の上を子どもらが遊びまわる。
子どもらにとっても日本人は珍しいのか、やたらちょっかいを出してきた。
途中、車は釘を踏んでしまいパンクしたが、そこに適当なネジをはめ込み、自転車用の空気入れで空気を入れのりきった。
そして8時間かかり遺跡の街カラコルムに到着した。
カラコルムで遺跡を見学し、そこには2泊した。
そしてツェツェルレグという街に向かった。
ツェツェルレグまでのバスもワゴン車で、フロントガラスに無数のヒビが入っているものだった。
ツェツェルレグまでは私以外に行く人がいなかった。
モンゴルのバスは、ある程度人数が集まらないと、出してくれない。
仕方なく、バスをチャーターするはめになり料金も高かった。
乗客は私1人なのに、ドライバーの他、3人の男が乗り込んできた。
最初その理由が分からなかったが、この車は押しがけしないと、エンジンがかからなかった。
他の男たちは、そのためにいるらしい。
ここでも2回パンクした。
そのときは、タイヤのチューブを器用に取り出して、穴の空いている部分に補修用のテープを貼り、修理した。
タイヤ交換とういうのは、最後の最後の手段らしい。
そしてツェツェルレグまで6時間を要し、そこからさらにジープをチャーターしてここまで辿り着いた。
その場所はウランバートルの西、約500キロ、ツェンケル・ジグールという温泉のあるツーリストキャンプである。
周りに見えるのは丘と草原、それに草を食べている馬、羊、牛、ヤクたちだけだ。
もともとここへ来たのは、北京以来浴びていないシャワーを浴びたかったからだ。
そしてここに温泉があると聞き、ジープをチャーターしてやってきた。
ここへ着くと、日本人らしき男性3人が日光浴をしていた。
こんなところにも日本人が来るのかと驚いて話し掛けてみた。
3人ともその格好からいってバックパッカーと思ったが、彼らは仕事で来ていた。
それもTVの取材だという。
3人うち1人が役者で、あとの2人はスタッフだ。
その役者のHさんが、モンゴルを旅して、現地の人たちと触れあうところを、あとの2人がビデオに収めるそうだ。
Hさんには、ガイドが1人いた。
Hさんのガイドのモンゴル女性は、まだ若かったが、英語もうまく頭もいい。
日本語も堪能であったが、TVの中では彼女は日本語はできないことになっていて、
彼女と話すときは英語を使うとのことだった。
ここは温泉が有名なので、もちろん温泉のシーンも収録する。
私は収録の邪魔をしては悪いと思い、すぐに温泉につかることにした。
収録が夜の7時からと聞いていたので、その前に済ましてしまおうと思ったのだ。
お湯を浴びるのは10日ぶりくらいだろうか。
お湯に浸かるのは日本以来なので、1ヶ月ぶりである。
温泉のつくりは、日本のそれを真似たもので、露天風呂は大きな石で囲ってある。
遥か彼方には地平線が見え、草原では馬が草を食べていた。
こんなにゆったりした気分になったのは久しぶりだった。
まさかモンゴルで温泉につかれるとは思っていなかったので、それが余計に私の気分を解放していたのかもしれない。
私が十分に温泉を堪能して出てくると、例の3人がちょうどやってきた。
これから収録するという。
『鉄郎さんも一緒にどうですか?』
という言葉に私は戸惑った。
別にTVに顔が出て困るわけでもないが、そんな体験をしたこもなく、かといってしたいと思ったこともなかった。
しかし、旅番組がどうやって作られるかという事には興味があり、安易に引き受けてしまった。
最初、役者のHさんが、
『今日、ここで会った鉄郎さんです』
と簡単にビデオカメラに向かって紹介してくれて、そのまま温泉に行った。
温泉にはすでにツーリスト・キャンプの女性従業員が3人入っていて、そこにHさんと私がお邪魔した。
要するに混浴である。
彼女らは肌が白く、みんな若い。
バスタオルで体をすっぽり隠してはいたが、やはり目のやり場に困り緊張する。
私は初めての混浴と、初めてのTV出演ですっかり舞い上がってしまった。
旅のドキュメンタリー番組なので、台本などもない。
ただ「楽しくやりましょう」と言われただけで、私は何を喋ったらいいのか困ってしまった。
彼女らとのコミュニケーションは英語だが、もともと得意でない英語は、さらに輪をかけて出てこなくなり、私の喉でつまって、何を喋っていたのか、あまり憶えていない。
ただHさんが、旅の事など質問してきて、それに答えるのがやっとだった。
その後も食事のシーンが続き、私もHさんたちと一緒に食べた。
モンゴル料理がゲルのレストランに並び、これもカメラを回しながら食事をする。
ここでも、「楽しい食事にしましょう」と言われただけで、特に指示はない。
料理は、ボーズという揚げ餃子の親分みたいなものや牛肉のステーキなど、肉料理のみであった。
Hさんは何故か日本から醤油をもってきていて、それをビデオカメラにアピールしながらステーキにかけていた。
「モンゴル料理は味が薄いので、醤油があると便利だ」ということらしい。
理由を聞くと、それがスポンサーである旅行会社からの要望らしい。
何故旅行会社と醤油が関係するかは分からない。
食品会社も一枚かんでいるのであろうか。
私も醤油をもらってかけてみた。
ステーキには、十分味がついていたが、さらに醤油の味が重なり微妙な味であった。
まずくはないが、醤油をかける必要もないような気がした。
もちろんHさんは美味そうに食べていた。
やはり現場というのは、どこの業界でも大変そうである。
その頃になると、もうカメラも気にならなくなり、Hさんや、Hさんのガイドともいろいろと話ができた。
沈黙が少し続くと、スタッフがカメラを止め、Hさんに
『次、この話題ふってみようか』
なんて言って撮影は続いた。
そしてHさんのガイドが
『この後、外でコンサートがあります。みなさん一緒に見ましょう。』
という一声で食事のシーンは終わり、撮影は一時終わった。
その間に馬頭琴の奏者がやってきて、スタンバイしている。
馬頭琴とは、モンゴルの民族楽器で、中国の胡弓と良く似ている。
弦の付け根の部分に、木彫り馬頭がついている。
その演奏は夜の9時過ぎから始まった。
ここは日が長い。
10時くらいにやっと暗くなるのだ。
キャンプの前の草原に民族衣装を来たモンゴル人が3人いた。
そのうちの1人の女性が歌い手で、もう1人の女性がモンゴル式の琴を操る。
そして、男性が馬頭琴の奏者だ。
そのコンサートを聞いているのは、ツーリストキャンプの従業員数名と、Hさんたちと、私だけである。
ほとんどプライベートコンサートである。
最初に馬頭琴とモンゴル式の琴に合せて歌が始まった。
夕暮れの光のなか、甲高い声が流れていく。
それはモンゴルの伝統的な歌らしい。
民謡のようなものであろう。
そしてモンゴル式の琴と馬頭琴の協奏。
そのメロディは自然のことを唄っているそうだ。
それはモンゴルの山であり草原であり、ヤクや羊たちのことであろうか。
最初は優しく始まり、徐々に力強く、そしてまたゆったりと消えるように終わり、最後にホーミーと続いた。
ホーミーとは喉を震わせて、低い声を出すものだ。
それは歌というよりは楽器といったほうがいいかもしれない。
同時に彼は馬頭琴を弾いた。
そのメロディはもちろん聞いたこもない。
しかしそれはどこか懐かしい郷愁を伴って、私の身体に入ってくる。
そしてその調べは草原へと吸い込まれる。
私は何の脈絡もなく、日本の事を思い出していた。
友人のこと、香港で別れた恋人のこと。
そして3月までやっていた仕事のこと。
私はある知的障害者の施設職員として働いていた。
養護学校を卒業した彼らのほとんどは、どこかの施設に通所あるいは入所して、大して変化のない生活を、何年間も送らざるを得ないケースが多い。
彼らのその姿は、人間らしく生きるとことはどういうことかを、いつも私に問い掛けているようだった。
その問いに私は今でも答えられないでいる。
いろいろな思いが私の思いも駆け巡り、もう何を考えているの分からなくなり、最後には真っ白になった。
モンゴルでは、何も見ていないという思いがあった。
確かに草原の美しく私を惹き付けたが、それ以上のものはなかった。
しかし草原でのホーミーは、その思いを消してくれた。
『これでやっと次に進める』
そんな思いが湧き起こる。
その夜は、満天の星空が私を迎えてくれた。