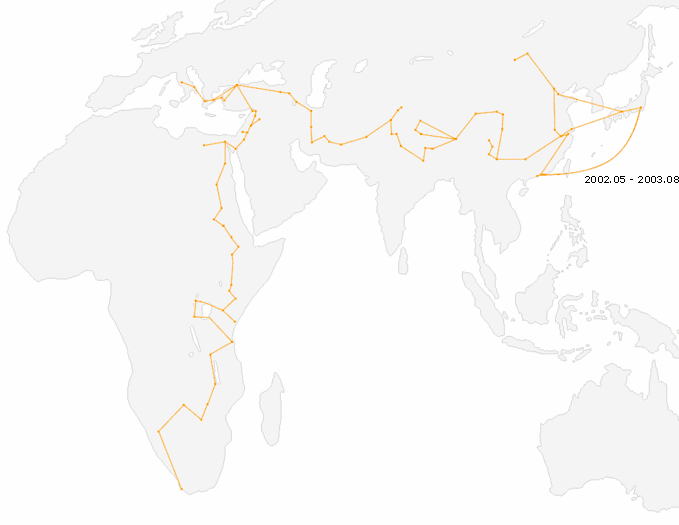旅でこんなにも急いだことはない。
昆明からラサまでの陸路を、わずか1週間かけて急いだ。
その間、宿に泊まったのはわずか2泊である。
あとは、夜中も移動を続けた。
急いだ理由は、8月8日にラサのデプン寺というところで、大タンカ(仏画)の御開帳があると聞いたからである。
せっかくラサに行くのなら、1年に1回のそれを見てみたいと思った。
そして、ラサまでの道中には、Hさんが一緒にいた。
Hさんが昆明に戻ってきたことは、昆明の手前の街、大理のネットカフェで知った。
Hさんは香港で盗難に遭い、てっきり日本に帰国したか、タイあたりに飛んだと思っていたが、陸路でラオスからタイに入るため、昆明まで戻って来ていた。
そして、私も中旬から成都のルートを、雨のため諦め、一旦昆明に戻って来ていたのだった。
本当なら西寧で会うはずだったが、盗難と雨という偶然で昆明で再び会うことになった。
香港でのHさんの盗難は、シングルルームのなかで、真夜中に起きたらしい。
香港はビルが密集している。
日本では考えられないほど、ビルとビルが並んで建っていて、配管などを利用すれば、簡単に隣のビルに渡れるのだ。
Hさんのゲストハウスのビルも、隣のビルと1Mほどしか離れていなかったらしい。
そして真夜中、窓から8階のシングルルームに忍び込まれ、テーブルの上に置いてあった貴重品を盗まれてしまった。
TCも領収書ごと盗まれ、再発行もきかなかったらしい。
もちろん、いつもなら貴重品を机の上に出すことなどない彼だが、昆明から香港まで一気に移動した疲れで、貴重品をそのままに、寝てしまったらしい。
まさか窓から忍び込まれるとも思わず、鍵もかけていなかったようだ。
彼のその話を聞いて、私は返す言葉がなかったが、彼は思いのほかあっけらかんとしていた。
起こってしまったものはしょうがない、という感じだった。
盗難のため、手持ちのお金がだいぶ心細くなり、チベットを諦めた彼だったが、やはりチベット、そしてカイラスは諦め切れないようだった。
そして結局、カイラスを目指し、行けるとことまで行くということになった。
昆明からラサを目指す場合、一般的にはゴルムドという街まで列車で行き、そこからバスに乗り換えることになる。
私たちはまず、昆明を13時に出て列車で成都に向かった。
成都には翌日の8時に着いたが、そのまま14時の列車に乗り換え、蘭州まで行った。
蘭州についたのはさらに翌日の15時で、その日の17時の列車で西寧まで強行した。
西寧に着いたのは21時くらいだった。
まるまる2泊3日の列車の旅である。
列車の移動は全て硬座だった。
硬座とは中国の列車の中で1番安く、いわば3等である。
この中国の硬座は、旅行者にえらく評判が悪い。
私も移動はいつも、硬臥という2等のベッド付きだったので、硬座にはある意味興味があった。
実際の硬座に乗ってみると、なるほど、なぜ評判が悪いのかが良く分かった。
乗客たちは絶えず何かを食べていて、そして床や窓の外にごみを捨てる。
中国人たちが良く食べるのはひまわり種で、その殻が床に散乱していた。
2時間に1回くらい掃除係りの乗務員が、ほうきでごみを集めるが、その度に車両全体に埃が舞う。
トイレもすぐに水が出なくなり、便器には人糞が積み重なっていく。
とても快適とは言えないが、硬座がひどいということは、あらかじめ人から聞いていたし、慣れてしまえば別にどうということもなかった。
それよりも、座席がほぼ直角のシートで、2泊3日の移動で、ほとんど眠れないことの方が体にこたえた。
疲れ切って、西寧の宿にチェックインすると、そこにMさんという一人の日本人がいた。
ゴルムドからラサの正規のバスは、入域許可書が必要で約3万円と飛行機並に高い。
だからバックパッカーは正規ではなく、違法で中国人が利用するバスに乗せてもらったり、タクシーでラサへ行く。
もし違法で行って、検問所などで公安(警察)に捕まった場合、罰金をはらい、さらに正規のバスチケットを買わされることになる。
私たちは、違法でタクシーを利用するつもりでいたので、最低でもあと一人タクシーをシェアする人を探していた。
しかも、西洋人だと顔立ちですぐにばれる可能性が高いので、日本人がよかった。
彼もラサまでどうやって行くか迷っているところで、一緒に行くことになった。
さらに驚いたことに、彼もまたカイラスを目指しているという。
彼の「長い付き合いになりそうですね」という言葉通り、Hさん、Mさん共にカイラスを目指すことになった。
西寧からゴルムドまで1泊列車に揺られ、ゴルムドの駅前で、ラサまで行ってくれるタクシーを探した。
しかしこちらの言い値が高かったのか、なかなか見つからなかった。
タクシーを諦めかけたとき、ラサまで800元(約1万2千円)で行けるという男が現れた。
片言の英語ができるその男と交渉し、1人500元まで負けさせて、交渉はまとまった。
その男が言うには、昼間は検問があるので、明日の早朝に出発するのがいいという。
その男の言われるままホテルにチェックインして、翌日をまった。
しかし翌日の6時になっても彼は現れなかった。
7時になってもこない。
騙されたとも思ったが、まだお金を1円も払ってないのでそれもおかしい。
8時になって、やっと彼が現れた。
『検問はスルーできる、今調べてきた』
という彼の言葉は信用できなかったが、もうここまできたら、彼に全てを託すしかなかった。
ホテルに横付けされていた車はフォルクスワーゲンのセダンで、運転手は色黒の痩せた男だった。
彼がおもむろに見せた身分証明書には確かに公安と書かれてあり、一瞬はめられたと思ったが、交渉役の男が言うには、公安が小遣い稼ぎのために、ラサまでのドライバーをやっているとのことだった。
チベットに入るパーミットを法外な値段に設定し、それをかいくぐってチベットに入る旅行者を捕まえる公安がいて、さらにその旅行者を闇でラサまで連れて行き、小遣いを稼ぐ公安がいる。
中国とは全くわけがわからない。
法律を犯しているというこちらの緊張感とは裏腹に、ドライバーは悠長に朝食を取り、サングラスを買ったり、奥さんを子どものいる幼稚園まで送ったりして、さらに中国人の旅行者を1人乗せ、やっと11時にゴルムドを出発した。
そこからラサまでは最初20時間と言っていたが、38時間かかった。
最初は景色を楽しむ余裕もあったが、日も暮れた頃になると、とにかく早く着いて欲しいと思うだけだった。
途中、検問は無事に通過したが、工事で何時間も待たさせたり、中国人が高山病にかかり頭が痛いと言って安宿で仮眠したり、パンクやエンジントラブルもあり、とにかく長く疲労も限界だった。
ラサに到着したのは、ゴルムドを出た翌日の深夜1時。
闇のなかのラサの街並みは、あまりに他の中国の都市と変わりがなかったが、そんなことを考える余裕もなく、泥のように眠った。
とくかくラサに着いた。
それだけで十分だった。
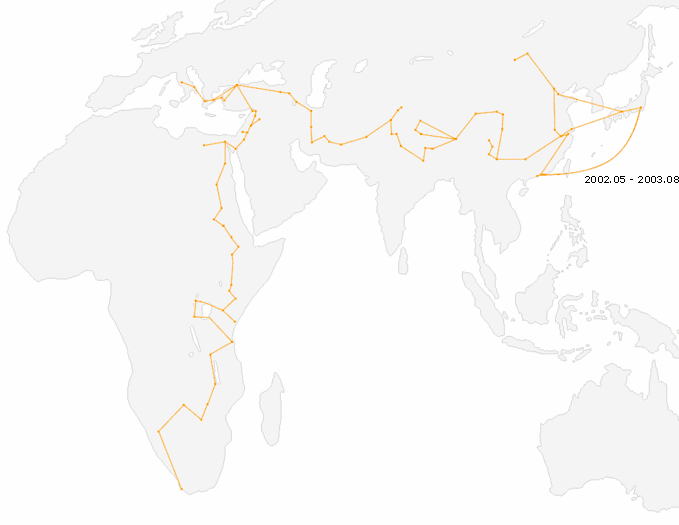 鉄郎 初めての海外旅行は22歳の時。大学を休学し半年間アジアをまわった。その時以来、バックパックを背負う旅の虜になる。2002年5月から、1年かけてアフリカの喜望峰を目指す。
鉄郎 初めての海外旅行は22歳の時。大学を休学し半年間アジアをまわった。その時以来、バックパックを背負う旅の虜になる。2002年5月から、1年かけてアフリカの喜望峰を目指す。