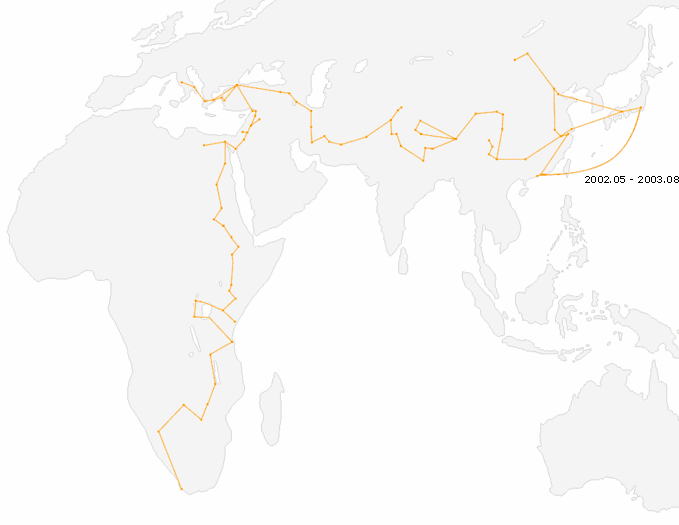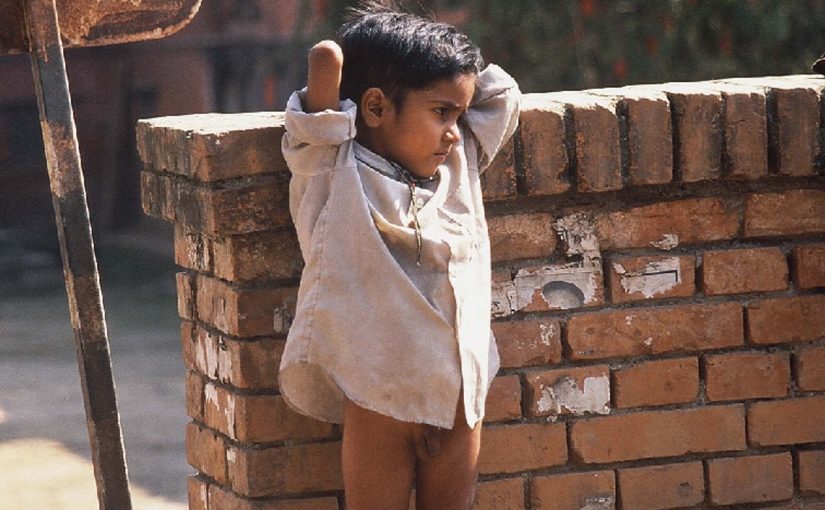バラナシには怪しい日本語を話す輩はくさるほどいる。
もちろん彼らの全てとはいわないが、たいていは土産屋に連れていってマージンをもらうか、ガンジャやハシシを高めに売りつけ、その差額でもうけようとする。
しかし彼はそんな輩とは明らかに違った雰囲気を持っていた。
彼の完璧な日本語にも驚いたが、それ以上に驚いたのは彼が日本の文化や習慣も知っていたことだ。
私は彼を最初から最後まで信用しきっていた。
残念ながら名前は思い出せないので、仮にラムと呼ぶことにする。
そのラムと会ったのはバラナシに着いてもう1週間以上もたったある日のことだ。
私は同じゲストハウスのシングルに泊まっている、Tさんと夕食を食べに出かけていた。
彼は会社員で、貴重な一週間の休暇でインドに来ていた。
Tさんは外見も、喋り方もいい人そのものだったためか、彼のインド旅行はトラブル続きだった。
日本から深夜のデリーに飛行機で到着し、そこからタクシーに乗ったはいいが、安宿街に向かうはずが、300USドルの高級ホテルに連れていかれたらしい。
もう外は真っ暗闇で右も左も分からず、結局300USドル払ってそこに泊まったと言っていた。
もちろん、300USドル分のホテルかといえば、せいぜい30ドルくらいの設備だったようだ。
次の日、やはりおかしいと思って、ツーリストオフィスに相談して、なんとか250USドルはもどってきたが、そのツーリストオフィスで、今度はタージマハルの250USドルのツアーを組まされたと言っていた。
もちろんそんな高額なツアーがあるわけない。
今思えばそのツーリストオフィスも、偽物だったかもとも言っていた。
そんな彼といっしょに、どこかおいしそうな店を探していると、インド人の青年が声をかけてきた。
背は低いが、筋肉質でがっちりした体つきだった。
『どちらへ行かれますか?』
という完璧な日本語だった。
そしてTさんが、
『どこかヌードルスープを食べれる店を知りませんか?』
と聞くとそのインド人青年は、わざわざ店まで案内してくれた。
それがラムだった。
ラムは店まで案内するとまずこう言った。
『もしよければご一緒してもいいですか?
別にお金がほしいわけでも、何か売りつける気もありません。
私はバラナシ大学で医学を勉強してますが、日本語も勉強しています。
ただ日本語の勉強をしたいだけです。
もし「が」とか「は」とか助詞の使い方が間違っていたら、教えてほしいのです。』
と彼は丁寧な日本語で言った。
もちろん断る理由もないので、いっしょに食事をすることにした。
しかし彼は食事も飲み物の何も注文しないで、何もいらないと言う。
私がチャーイくらいおごるよと言うと、最初は断ってきた。
さらに私が薦めると、ラッシーを注文した。
その辺の一度断るところなど、極めて日本的だった。
食事をしながら聞く、ラムの話は面白かった。
『私は大学生ですが、日本語通訳の仕事もたまにやります。
NHKの取材班の通訳もしました。
緒方拳さんが来たときも案内しました。
そのときサイババの弟子がちょうどバラナシに来ていて、緒方さんは自分の将来をみてもらっていて、その時も通訳しました。
ちょっと、その内容は言えませんが、緒方さんはとても満足していました。
彼はとても紳士的でかっこいい人ですね。
それから鶴田真由さんの通訳もしました。
びっくりするほど、きれいな人ですね。
日本は大好きです。
いつか行ってみたいです。
たくさんのインド人が東京に行って働きたいと言うけど、私は京都に行きたいです。
あそこは日本の文化の故郷ですからね。
京都の鴨川で沐浴してみたいですね。』
そんなふうに、日本に対する憧れも語ってくれた。
私もここぞとばかりに、インドに対する疑問を、少々失礼かなとも思いながらもぶつけてみた。
しかしラムは嫌な顔もぜずに、答えてくれた。
『確かにカーストによる差別は憲法で禁止されています。
しかし、実際に全ての差別がなくなったともいえません。
やはり、職業カーストの枠から抜け出せず、親の職業を継ぐケースが多いです。
洗濯夫の子どもは洗濯夫に、リクシャ引きの子どもはリクシャ引きに、ヘビ使いの子どもはヘビ使いにといった具合です。
もちろん、自分で勉強し、努力し、他の職業に就くケースもありますが、まだ希なケースですね。
それから外国人が思うほど、カーストは悪いものじゃないと思っているインド人も多いです。
ずっとそれでやってきたわけですから。
それから結婚についてですね。
ご存知の通り、インドには花嫁が持参金を用意するのが習慣です。
その金額は、親の職業やカーストによっても様々ですが、それがトラブルの元になるのも事実です。
持参金が少ないといって、姑にいびられ焼身自殺したり、あるいは姑を焼き殺したりという事件は、インドではあまり珍しくありません。
持参金が原因で花嫁が夫を殺すなんてこともあります。
でも持参金はきっとなくならないと思います。
それをなくそうと運動している政治家もいますが、もう何千年も続いている習慣なのです。』
彼から聞く、インドの話は新鮮だった。
私はメモをとりながら、彼の話を聞いた。
それから旅行をする上での注意もしてくれた。
『インドでは残念ながら、旅行者をだます詐欺師が大勢います。
高額なツアーを組まされたり、お土産を何倍もする値段で買わせる連中もいます。
先日会った日本人の方は、デリーで400USドルも出して、シルクの布を何枚も買ってました。
見せてもらうと、せいぜい50ドルのものです。
お土産を買うならバラナシがいいと思います。
デリーで売っているものも、ほとんどバラナシの工場で作ってますので、ここで買ったほうが安いですよ。
この近くに旅行者用でなく、インド人が集まるバザールがあります。
もし、ピジャマやクルタ(インドの国民服)、シルクの布とか欲しいなら、よかったらこれから案内しますよ。』
ラムの申し出はありがたかったが、私は遠慮した。
昨日、何故だか考え事をしていたら、眠れなくなって一睡もしていないのだ。
私は疲れているからと断ったが、Tさんはラムと一緒にお土産を見に行くというので、私は一人ゲストハウスに戻った。
そして次の日の昼過ぎ、
『鉄郎さん、わかったよラムの正体が!!』
とちょっと興奮してゲストハウスのドミトリーにTさんが入ってきた。
『あの後、ラムが店を紹介してくれて、25ドルのショールを買ったんだよ。
シルクだから高いとラムが言ってて、そのときは俺もそう思ったんだ。
でもほんとにそんなにするのかなぁと思って、今その辺りの布屋に聞きにいったら、せいぜい5ドルだったよ。
2、3件きいたけど、どこも同じだった。
それで、事の顛末をしゃべったら、店員が、そいつは背が低くて、筋肉質で、日本がうまくて、NHKの通訳をやってたって言ってたろうって。
ここらではちょっと有名な詐欺師で、何人も日本人がやられてるらしいよ。
また騙されちゃったよ。
まったく・・・・』
私は、Tさんの話を聞いて、なんだかラムがそんな奴だとは信じられなかった。
なるほど、最初から土産屋に連れて行って、正当な値段よりも高く買わせて、後でその店からいくらかのマージンをもらう手口だというのはよくわかる。
しかし、私が引っかかったのは、彼の日本語と日本文化に対する知識だった。
ラムの日本語は明らかに、旅行者を食い物にする輩とはレベルが違った。
あれだけの日本語をマスターするのには、何年も相当な努力が必要だったはずだ。
それ以上に、日本の文化や地理を勉強するのだって、簡単なことではない。
それだけの努力のできる男が、なんで旅行者相手にそんなつまらない商売をしている のだろうか。
NHKの通訳はともかく、ツアーのガイドくらいならすぐに務まるはずだ。
いや、もしかしたら、そこにカーストの壁が存在したのかもしれない。
だからそんな事でしか生きていけないのかも・・・
私はそんなことをぼんやりと考えていた。
それにしても可哀相なのはTさんだ。
彼のなかのインドは、まさにさんざんだったようだ。