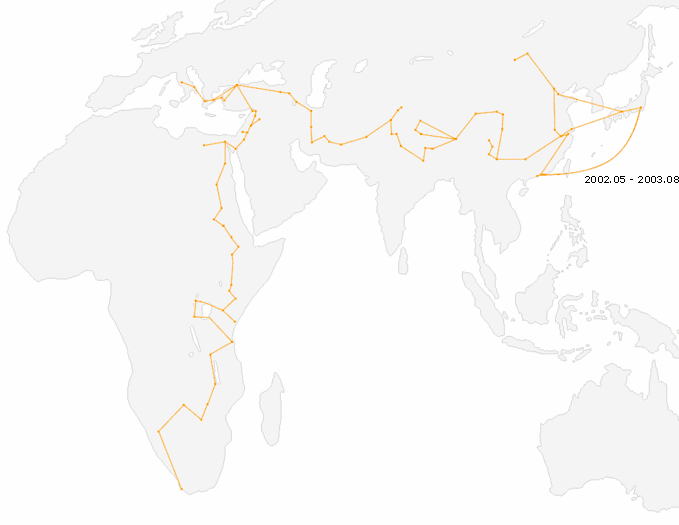イランからトルコに入国した私は、トゥバヤズットとエルズルムにそれぞれ1泊しただけで、ほとんど何も見ることなく、イスタンブールへと急いだ。
その途中にも見たい場所はいくつかあった。
黒海も見たかったし、サフランボルの旧市街で写真も撮りたかった。
しかし私は、そんなことよりも、早くイスタンブールに着きたかった。
私はそこである人と会う約束があったからだ。
そのために余裕を持ってイスタンブールに着いていたかった。
エルズルムから、雪景色のなかをバスは走った。
私とエミには約束があった。
旅に出ている間、週に一度は必ず手紙を書くというものだった。
私はそれを宿題みたいに思ってしまって、何回かさぼってしまったこともあったが、彼女に旅先で見たものや、感じたことを綴るのは、やはり楽しいものだった。
エミはその何回か届かなかった手紙のことを、私に言った。
私にとっては、ただ何となしに何回か書かなかった手紙でも、エミにとっては私と彼女をつなぐ、ほとんど唯一の約束だった。
いや、もちろん手紙が一通や二通届かなかっただけで、婚約を解消するわけもないことはわかっていた。
私が旅の途中にいろんな人と会い、いろんな経験をしたように、彼女も日常のなかで、いろんな人に会い、もちろん楽しいことばかりであるはずもなく、つらいこともあったはずだ。
エミが何かに苦しんでいたときも、私は旅をしていた。
そしていろんな出来事が重なり合って、やがてエミの心を動かした。
その一つが手紙だったとも言える。
私はその小さな積み重ねを怠ってしまったのだ。
そんなエミの気持ちを聞いて、やはりどうしようもなくやりきれなくなって、落ち込んだりもした。
それでも、昼間は二人でよくイスタンブールを歩いた。
きっと、他の人から見れば、やはり恋人同士に見えただろう。
新婚旅行に間違えられることもよくあった。
しかしその時の私たちの関係を表現する言葉を私は知らない。
恋人でもなく、かといって友人でもない。
そして喧嘩や口論をしたわけでもない。
お互いの胸の内はよく話した。
旅の話もしたし、日本での話も聞いた。
しかし、やはり、恋人ではなかった。
ブルーモスクやトプカプ宮殿、アヤソフィア博物館、メデューサの地下宮殿などを見てまわった。
エミの誕生日が近かったので、スケッチブックと色えんぴつを彼女に買って、それを持って、ブルーモスクの前の広場に行ったことがあった。
まだ、寒い時期だが、そこのベンチに座り彼女はブルーモスクをスケッチして、私はブルーモスクや、同じくその広場で佇む老女や少女の写真を撮った。
そしてエミの写真も撮った。
その時間は、何にも代え難い甘美なものに思えた。
イスタンブールを一通り見た後、私たちはセルチュクに行った。
エフェスという古代ギリシャの遺跡を見るためだった。
エミは遺跡に、特にギリシャのそれに興味があり、ずっとギリシャに憧れていた。
だからエフェスに行きその後、船でギリシャに渡る予定を立てていた。
セルチュクでも曇りや雨が続いたが、エフェスそのものは悪くなかった。
多分一人で行ったら大して興味をもてなかったかもしれない。
しかしエミと、かつて24000人収容できたと言われる半円形の大劇場の端まで行って、
『すごい、真ん中にいる観光客の話声が聞こえるよ。この頃から音響っていう考えがあったんだね』
とか、また、博物館を見て、
『彫刻を見るとこの時代の人たちは薄っぺらい服を着てるけど、寒くなかったのかな。だって私は寒くてエアテック着てるんだよ』
なんて話を聞くのは楽しかった。
そうして過去の人たちに思いはせることのできるエミを少し羨ましく思った。
ちょっと足を伸ばし、シリンジェ村というところに昔の街並みを見に行ったりもした。
その小さな村はワインが有名でそこでワインを買い、その夜は二人でエミの誕生日をささやかに祝った。
私はセルチュクのゲストハウスで思いがけない偶然に遭遇した。
そこのロビーで、日本の女子大生の2人組と話をした。
何の勉強をしているとかそんな話をしてるうちに、そのうちの一人がW大学の大学院生であることがわかった。
私はもしやと思って、
『H先生を知ってますか』
とたずねてみた。
H先生は、私の母校のゼミの教授で、今は学校を変わりW大学の大学院の教授だと聞いていたからだ。
もし私に恩師と呼べる人がいるとすれば、そのH先生以外に考えられなかった。
すると彼女は、意外にもH先生のゼミをとっていると言う。
私はその偶然になんだか嬉しくなった。
私はもうすぐ帰国するという彼女に、H先生宛ての手紙を託すことにした。
今でも年賀状だけは欠かさず出しているが、手紙を書くのは何年ぶりだろうか。
以前、休学して旅をしていたときにはよく手紙を書いた。
そのとき、H先生のゼミで、環境問題を勉強していたが、私はアジアの貧困という視点からそれを考えていた。
だからアジアを旅して、タイのスラム街の様子だとか、インドのカルカッタには歩けば踏んでしまうほどの物乞いがいるとか、そんな手紙を送ったのを覚えている。
私は手紙を書きながら当時のことを思い出した。
やはりあの時は若かった。
何も知らなかった。
けれども何も知らない分、何でもできるような気がした。
その後卒業し、いくつかの仕事を経験し、年齢的にもすっかり大人と呼ばれるようになった。
コンヤペンションで会った彼のことがふと頭をよぎった。
彼の憂さの晴らし方に私は若いなぁと思ったが、実際に彼はまだ若かった。
私にはそれはできない。
私はもう充分に年齢を重ねた大人だった。
少なくとも、年齢だけは大人になってしまっている。
私には、何かに逃げるなんていうことはできなかった。
それに、まだエミはまだ目に前にいるのだ。
しかし今の自分は、エミとの微妙な関係に振り回され、彼女の前でさえ、落ちこんだりした。
私は自分自身のことを狭量な男だと思った。
そんなふうに二人で旅をしったって、旅はいきいきとはしない。
少なくとも思い描いていた旅とは違う。
それによって、自分にとって貴重なはずの旅の時間どころか、彼女にとっても大切で、少なくとも楽しみだったはずの旅の時間をも台無しにしようとしていた。
エミは2月11日のイスタンブールから成田のエアチケットを持っていた。
トルコに来るのに往復の航空券を買ったのだ。
日本では通常、片道航空券の格安チケットを買うことができない。
いや買えたとしても、往復のそれより高くついてしまうこともある。
だから私も旅の最初、香港までの往復の格安航空券を買って、帰りのそれは捨てた。
エミはその便で帰国するかもしれない。
それはまだわからないし、それまでにはまだ20日ばかり時間がある。
私はもしかしたら、エミと過ごす最後の時間になるかもしれない残りの時間を、少なくとも彼女が
『いい旅だった』
と思い出せるようにしたいと思った。
それが自分のやるべきことだと思ったのだった。
それが最後の、私がエミにできることだとしても、やはりそうしたいと思った。
この後はギリシャに行く。
それはエミの憧れの地だ。
そこへ行けば何かが変わるかもしれない。
今の状況をひっくりかえすような何かが起こるかもしれない。
そんなことを思った。
東京だったら大雪という表現がふさわしいくらいの雪だが、バスはそんなことお構いなしにひたすら走る。
雪はきれいだった。
降りてくる雪が、窓ガラスにくっついて、その結晶が少しずつ、少しずつ溶けていく様子を、ずっと見ていた。
日本で雪が降ったって、そんなふうに見たことはない。
そんなことで、私は旅に出ているのだなということを、自分で認識する。
20時間くらいはかかったろうか。
昼頃にエルズルムを出発し、一晩かかり、イスタンブールへは、朝方に到着した。
イスタンブールのバスターミナルはあまりに巨大でどこかの空港を思わせる。
とにかく腹が減っていて、私はバスターミナルのなかの店で、パンとチャーイだけの簡単な朝食を食べた。
そのチャーイを飲みながら
『とうとうイスタンブールまで来た』
そんなことをいくら考えてもみても、やっとアジアを陸路で横断したという感慨はほとんどない。
香港から中国、モンゴル、ネパール、インド、パキスタン、イラン、トルコと、今まで越えてきた国の名前を思い浮かべてみる。
確かに遠くに来たという思いはあった。
しかし、なぜか達成感みたいなものはない。
それは自分でも不思議だった。
そして少し残念だと思った。
そんなことよりも、その人に早く会って、いろんな旅の話しを聞かせたいとか、どこへ連れていこうかとか、そんなことばかりを考えていた。
バスと路面電車を使い、安宿街まで来て、宿を探す。
ここには二つの有名な日本人宿があったが、まずはTREE OF LIFEという宿へ行ってみた。
絨毯屋の2階から4階までが宿になっている。
ドミトリーが男女別と聞いていたが、男性用がいっぱいだったので、女性用の部屋に案内された。
一度は、そこへ泊まろうかとは思ったが、結局断って別の宿を探すことにした。
もともと男女混合のドミトリーなら問題ないが、部屋が女性用でなんだか落着かなそうだったし、9時を過ぎてもカーテンを締め切っていて薄暗く、ほとんどの人が寝ている様子で、こそこそと荷物をほどくのもなんだか面倒なことに思えた。
そして、もう一つの日本人宿であるコンヤペンションへ行ってみた。
見てみると、なんだかそっちの方が落ち着きそうな気がした。
なにより団欒室がTREE OF LIFEより広く、靴を脱いであがるようになっていて、くつろげそうだった。
別に私は日本人の溜まり場となっている宿が、嫌いというわけでもないが、特別好きというわけでもない。
いろんな人間がいて、彼らと関わるのが楽しくて、そこに行くときはある。
しかしそれ以上に、たいてい日本の書籍があるし、特に情報ノートがあるので利用することは多い。
私はこれから先のルートの情報をほとんど持っていなかったので、イスタンブールでは日本人宿に泊り情報を集めると決めていた。
そのコンヤペンションはエリフという日本語を話すかわいい女性スタッフがいるせいもあって、日本人の、特に男性の溜まり場になっていた。
私が着いたときも8名ほどの日本人がいて、女性は一人だけだった。
私が団欒室でくつろいでいるとき、ある大学生の男性と話をした。
名前は聞いたが覚えていない。
彼は大学を休学し、上海から陸路でユーラシア大陸を横断し、スペインあたりから飛行機でイスタンブールまで戻ってきたところだった。
何かのとき、彼の恋の話になった。
彼は恋人を日本に残し旅に出た。
メールや手紙を欠かさなかったことには、別に驚きもしなかったが、週に一度はかならず国際電話を入れていたという話には恐れ入った。
それだけで相当の金が飛んでしまうだろう。
そして一ヶ月ほど前、ヨーロッパのどこからか、彼女に国際電話を入れたときに、新しい彼ができたことを突然宣告されたらしい。
その後は飲めない酒を飲んで、吸えない煙草を吸っていると、ビールを飲んで真っ赤になりながら話してくれた。
私はそんな彼の憂さの晴らし方が、若いなぁと思った。
別にそれがいいとか、悪いとか言うつもりはないが、ただ若いなぁと感じた。
『そんなのよくある話だよ』
と私は彼に言った。
別に冷たく言ったつもりもなく、本当にそう思ったからだ。
すると彼は、
『そんなこと言わないでくださいよ、真剣に落ちこんでるんですから』
と彼が言う。
『いや、よくある話だよ。俺も学生の時に似たようなことがあったよ』
と言うと、彼は私の隣に座り、ぜひその話を聞かせて欲しいと言う。
別に聞かせて面白い話でもないが、困る話でもないのでその話をした。
それは、私が学生のときに休学して旅に出たが、そのとき日本に残してきた彼女が、帰国したら別の男の彼女になっていたという、別に面白くもなんともない話だ。
彼は真剣に私の話を聞いた後、
『今はどうなんですか?』
と言うので、
『彼女いるよ、婚約してる。明日イスタンブールまで来るよ』
と答えると、彼は少し安心したように、
『婚約ですか。じゃあ、自分も結婚できますかね』
と言う。
そんなことは、私に聞かれてもわかるわけもないことだが、
『できるよ、まだ若いんだし。仕事だって恋愛だって、いくらだってできるよ』
と私は答えた。
彼は、
『なんか・・・すっきりしました。ありがとうございます』
なんてふうに丁寧にお礼を言っていた。
そんなことを言われる覚えもないが、まあ、悪い気はしない。
私がイスタンブールまで急いだ理由はその婚約者に会うためだった。
彼女は、いやエミは、仕事を辞め飛行機に乗り、明日イスタンブールに着く。
そして、イスタンブールから、南アフリカの喜望峰まで一緒に行き、帰国したら結婚する予定だ。
すでに結納もすませてあったし、式場も予約していた。
私は旅の途中、エミとの将来をあれこれとよく空想していた。
まずは仕事をどうするかを考えなくてはならないのに、そんなことよりも、鎌倉に一緒に住みたいとか、犬を飼いたいとか、車を買うなら4WDを買って、キャンプに行きたいとか、次の夏は花火を見に行きたいとか、そういったおよそどうでもいいような、それでいて楽しいことばかりをよく考えていた。
私は彼女と過ごすはずの将来を疑うことはなかった。
次の日、空港までエミを迎えに行った。
やがてゲートから出てくる彼女を見つけた。
しかし約半年ぶりの再会というのは、あまりにあっけなく、普通だった。
『まあ、ドラマじゃあるまいし』
と思ったが、その理由は別にあったことを、その数日後、私は知ることになる。
私はエミと合流して宿変えた。
少しランクが上の、といっても安宿には変わらないツインの部屋に移った。
そこで5日くらいいただろうか。
私はエミと再会して以来、日記を書くことをやめてしまった。
もちろん書くことはできただろうが、書けば、自分がまるで泥の中に沈んでいく様子を書くはめになるのでやめてしまった。
だからエミにそのことをいつ言われたのか、正確に思い出すことはできない。
会った次の日か、あるいはその次の日だっただろうか。
エミが仕事も辞めてイスタンブールまで来た理由は、待ちきれなくなったからだ。
少なくとも数ヶ月前に、彼女が航空券を予約したときはそうだったろう。
しかし、今は違う理由で来たと彼女は言った。
彼女自身、自分の気持ちがよくわからなくなってしまったと言った。
『なんだか恋愛感情から、家族や兄弟みたいな感情になってしまったみたい。だからもう恋愛も結婚もできないかもしれない。』
それを確かめるために来たと彼女は言った。
それは別に、都合のいい、別れる理由でもない。
そうだとしたら、わざわざイスタンブールまで来るわけがない。
エミは半年旅をするつもりで、装備も半年分のものだったし、保険だって高い金を出し、半年分のそれに加入してきたのだ。
『最後まで一緒に行くかもしれないし、途中で帰るかもしれない。もし帰ったらもう結婚はできない』
そう言った。
そのエミの感情の変化というものは、正直に書けば、私にはよくわからないものだった。
いや、人の気持ちを正確に理解できる人間なんているわけがないのはよくわかる。
しかしそれは私が男だからわからないのだろうか。
それにしても、私は彼女の気持ちが、やはりよくわからなかった。
別に好きな人ができたわけでもなく、恋愛感情から兄弟みたいな感情とはどういうものだろうか。
実際にエミは、例え婚約を解消したとしても、私と連絡が取れなくなることだけはしないし、絶対にしたくないと言った。
そしてその変化した気持ちを確かめるために、エミは仕事も辞めてわざわざイスタンブールまで来た。
だったら何故・・・と私は何度も思った。
いやその時のエミの気持ちは、これを書いている今なら少しは理解できる気がする。
きっとそのときはわかりたくもなかったのかもしれない。
あと、数ヶ月して旅が終わったそのときには、きっと正確にわかるのだろう。