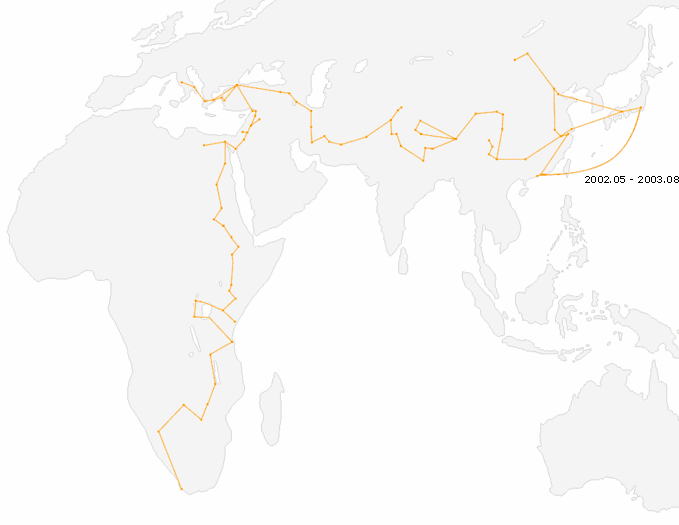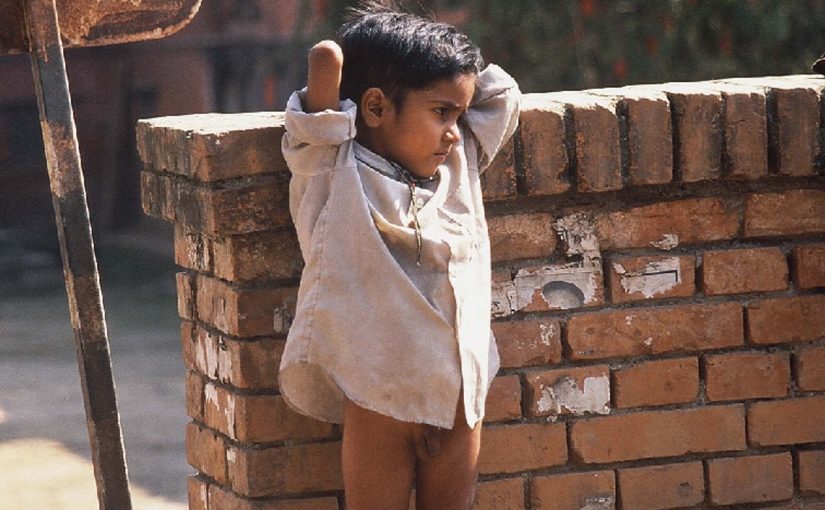誰が言い出したのかはわからないが、バックパッカーの間で語られる「3大バカ民族」というのがある。
あくまで、噂話の域を出ないものであり、あまり上品な言い方ではないし、言われた方はいい迷惑どころか激怒しそうなものだ。
しかし、平たく言えばそれらの民族の国は、旅行の行き先としては人気があっても、旅をする上ではトラブルも多いということだろう。
そしてトラブルに巻き込まれ、しまいには、彼らに対する反感がつのり
『奴らバカなんですよ』
ということになる。
その3大バカ民族は中国人、インド人、そして私のいるエジプト人である。
もちろん、私もそう思うかと言われれば、そんなことはないと思うが、私自身の旅を振り返っても、なるほどと思わないでもない。
まず中国であるが、ここはほとんど英語が通じない。
私の訪れた国々のなかでもだんとつである。
「one two three」さえ通じない。
都会ならともかく、地方に行くともう絶望的である。
彼らは漢字を使うので、筆談という手もあるが、これは思っているほど通じず、なにより誤解が生じる危険もある。
従って、中国を貧乏旅行するには、片言の会話を覚え、数字を覚え、旅に臨むことになる
私も、これが欲しいとか、どこに行きたいとか、それくらいの中国語は覚えた。
しかし、やはり通じないことの方が多い。
これは私が実際に実際に体験したことだが、マクドナルドでハンバーガーを中国語で注文した。
覚えてたての中国語で恐る恐る喋る。
すると、店員は私の言っている意味がわからずに、
『アー?』
と言う。
その『アー?』は普通の『アー?』ではなく、「何だお前は中国語も喋れずに中国にいるのか」という風に聞こえる『アー?』なのだ。
はっきり言ってしまえば、非常に不愉快に聞こえるのだ。
恐らくは「何て言ったの、もう一回言ってくれる?」という意味を込めた『アー?』
だと思うだが、何度聞いても不愉快に聞こえてしまう。
頭ではわかっていても、感情的はやはり腹立たしい。
これは慣れるまで時間がかかった。
さらに中国人はマナーが悪く、道端やバスや列車のなかでも痰ははくし、列には並ばない。
バスのなかで親が子供に小便をさせている。
女性は大股を開いて座る。
一度列車で、すごい美人を見たが、その股を大いに広げて座る姿に、心も萎えた。
とにかくマナーの悪さは、指折りであろう。
次にインドである。
この国もトラブルの宝庫である。
まず、タクシーやリクシャの類は、ひたすらぼったくろうとする。
特にひどいのが、デリーの空港からプリペイドタクシーである。
まず、空港のプリペイドだからといっても、安心できない。
ぼったくろうとするので、あらかじめ料金を知っていないといけない。
そしてやっかいなのは目的地に行ってくれないということだ。
特に深夜にデリー空港の到着した場合は要注意だ。
たいていの旅行者は安宿街のあるメインバザールへ行ってくれと言いタクシーに乗るが、深夜でゲストハウスは閉まっているとか、最近テロがあったとか、なにかと理由をつけて、高級ホテルへ連れていって、マージンをもらおうとする。
しかも200ドルのホテルに連れていかれたが、実際はせいぜい30ドルほどのホテルだったりする。
さらには、偽者の政府ツーリストオフィスに連れていき、法外な値段のツアーを組まされたりする。
特に女性の一人旅などでは、数人に囲まれてしまえば、詐欺だとわかっていても、やはりお金を払わざるを得ないことも多いと聞く。
そして最後が私のいるエジプトである。
タイプとしてはインドと似ている。
物の物価がないのだ。
土産屋などで、外国人と見ると10倍くらいの値段は言われることも少なくない。
さすがに日用品では、そこまでの値段を言われることは少ないが、それでも水1本買うにしても、せこくぼってくる店があるのも確かだ。
だからゲストハウスの情報ノートには、「正直屋を発見 ここならぼりません」なんていう情報まである。
正直屋というのは、適正な値段で買える雑貨屋という意味だ。
しかもやっかいなのは、地元の住民までがそのツーリストプライスというのを認めている節があるということだ。
それは特に観光地がひどい。
例えばアブシンベル神殿で有名なアスワンでのことである。
その街から、ナイル川を渡るとヌビア人の住む村があり、私は何度かそこへ写真を撮りに行った。
ナイル川を渡るには、対岸まで乗合ボートが出ていてそれに乗らなければならない。
たいてい1エジプトポンドで乗れる。
これで約20円だ。
こんなに安いのかと思ってしまうが、実は地元の人は0.25エジプトポンドで乗っている。
日本円に直すとわずか5円である。
私も最初にこのボートに乗るときに1ポンド払ったが、その後、他の旅行者と話していて、実は0.25エジプトポンドであることを知った。
しかしこの手の本当の値段を知るのはかなりやっかいだ。
後日ボートにのって、0.25ポンドきっかりのコインを出すとなにも言われなかったが、帰りに1エジプトポンドを出し、お釣りをくれといっても、なかなかくれなかった。
私がもめていると、他の乗客までが、1ポンド払えと言う。
つまりは、決められたツーリストプライスというわけではないが、地元の人と、ボートの職員暗黙の了解のもとに成り立っている外国人料金というわけだ。
同じようなことは、ここらで食べることのできる、ファラフェルというサンドイッチを買うときや、チャーハンとパスタをトマトソースで味付けしたような、エジプトの国民食であるコシャリ屋に入ったときにもあった。
カイロでそういうことは、まずないが、観光地ではひどい。
シリアからエジプトまでのルートは、南下するほど人が悪くなり、エジプトでピークを迎えるとよく言われる。
とはいえ、私はそれほど心配してはいなかった。
今までの旅でも、物価の決まっている国ほうが少なかったし、初めての国であっても、何かを買う前に、いくつかの店で値段を調べてから買えは、おおよその物価もつかめてくる。
それに、私としては、ぼったくろうとする連中がそれほど嫌いではなかった。
もちろんぼられると、腹立たしい。
しかし、お金を払うときは、納得して払うわけだから、こちら側の責任もある。
また、持ってる奴からは一円でも多く取ってやるといって、彼らのパワーみたいなものも、まんざら嫌いではないし、彼らとの交渉も旅でしか味わえないものである。
しかし、旅行者のなかには、徹底的に、そして頭からエジプト人は信用していない人もいた。
『あいつら、頭おかしいんですよ』
とまで言う人もいた。
旅をする上で警戒心とは、ある程度必要だが、そこまでいくと見苦しい。
だったら、エジプトに来なければいいのにと思ってしまうのは、余計なおせっかいだろうか。
さて、前置きが長くなったが、その3大バカ民族のエジプト人に、私もまんまとやられたのである。
別に巧妙な手口だったわけはなく、今考えると私が間抜けすぎた。
あるいは、旅慣れているという油断があったのかもしれない。
この旅で知らず知らずのうちに、小銭をぼられていることは、いくらでもあっただろうが、やられたと実感したのは、これが初めてであった。
その日、次の目的地、ルクソールまでの夜行列車の時間まで、カイロの街をふらふらと歩いていた。
もう夕方に差し掛かった頃だ。
その男が声をかけてきたのはそんな時だった。
宿の近くの交差点だった。
『ハロージャパニーズ、どこへ行くんだ?』
と声をかけてきた男は、50歳くらいのメガネをかけた中年で、片足をすこし引きずって歩いていた。
『シャイをご馳走したいんだ』
という唐突な誘いに対し、
『これからジュースを飲みに行くんだ』
と無表情に答えた。
どうせこの手の輩は、結局は土産物屋の客引きだったりする。
しかも初対面の、最初の言葉が、シャイを飲もうだなんて、どう考えても怪しすぎる。
それでも彼は、
『だったら待っているから、少し話をさせてくれ』
とめげない。
私は彼を無視して、いつも飲んでいる生ジューススタンドに行き、オレンジジュースを飲んだ。
この時期のカイロは、暑くも寒くもなく、日本の春先みたいな気候だが、目の前でオレンジを絞ってつくる新鮮な生ジュースは、体に吸収されるような感じで旨い。
しかも約20円と安い。
もちろん、椅子なんてないから、路上でグビグビと飲む。
そしてきた道を引き返すと、彼は同じ所で待っていた。
『約束通り待っていた、シャイをおごるよ』
『約束なんてした覚えはない。
あなたが勝手に待っていただけだ』
と我ながら冷たい言い方をした。
『5分でいいんだ。5分間だけ話をさせてくれないか』
『なんでそんなに私と話がしたい。盗られるような金は持ってないぞ』
と私が言うと、彼は続けた。
『そんな気はない。
今度娘が日本へ行くことになったんだ。
だから日本のことを少し教えてほしいんだ。
君は日本人だろう』
当然、そんな話を私は信用しない。
『だったら他をあたってくれ、今は時間がないんだ』
実際に時間がなかった。
列車の時間まではまだずいぶんと余裕がるが、宿に帰ってパッキングをしておきたかった。
私が、立ち去ろうとすると、彼はメモに自分の住所を書いて私に渡した。
『暇なときに、手紙をくれないか。何でもいいから日本のことを教えてほしい』
会って、数分しか経っていないこの男に、手紙を出すはずもないのだが、私は彼の住所の書かれたメモをうけとり、もしかしたら彼の言っていることは本当かもしれないと思い始めた。
もしこの男に、例えば土産物屋に連れて行き、何か買わせてマージンをもらうだとか、人気のないところに行き、仲間を呼んで金を奪うだとか、そういった目的があるとしたら、私をその目的の遂行できる場所へ連れていかなければならない。
ここで私が無視して立ち去ってしまえば、その時点で彼にとって私は無用の存在になるのだ。
つまり、手紙なんてもらってしょうがないのである。
ところが、彼は手紙でもいいから日本のことを知りたいという。
それで彼の言っている、娘が日本に行くというのは本当の話かもしれないと思ったのだ。
『わかったよ。でも私は今日の夜行列車でルクソールに行くから、あんまり時間がない。
でももちろんシャイを飲むくらいの時間はある。
シャイだけ付き合うよ』
そういうと、彼は握手をして、
『ムハンマドだ』
と名乗った。
ムハンマド。
イスラム圏ならどこにでもいる名前だ。
5分ほど歩き、路地裏にあるシャイ屋に案内された。
エジプトではチャイではなく、シャイという。
といっても他のイスラム圏同様、ミルクは入れない。
たっぷりの砂糖と、ミントを入れたりする。
そのシャイ屋の場所は、外国人は寄り付かないような雰囲気ではあったが、近くの通りは良く歩く道なので、全く知らない場所というわけではなく、特に不安もなかった。
彼はシャイを飲み、私はコーヒーを飲んだ。
挽いたコーヒーと、砂糖をグラスに入れ、コーヒーの粉が沈むのを待って、上澄みを飲む。
アラビアコーヒーだ。
『オリビアは日本へコンピューターの勉強へ行くんだ。
場所は長崎だ。
ビザを取るのに苦労したよ』
オリビアというのは、ムハンマドの娘の名前だ。
そして彼女の行き先は長崎だ。
この時に気付くべきだった。
いや、その長崎とう地名にピンとこなかったわけではなかったが、そのときはそんなに深く考えなかったのだ。
日本のなかで、最もよく知られている地名といえば、なんといっても東京である。
首都であるから当然だ。
その次は大阪。
大阪には国際空港もあるし、バックパッカーには大阪出身の人が多いというのも理由の一つかもしれない。
そして、横浜もワールドカップで有名になった。
その三つを除いて有名な都市名というと、広島と長崎がくる。
特にイスラム圏では反米感情も手伝って、アメリカの悪行が行われた場所として、驚くほど広島、長崎という街の名前が知れ渡っている。
街を歩くいていると、
『コンニチハ、サヨウナラ、ヒロシマ、ナガサキ』
と、とりあえず知っている単語だけを並べて、挨拶してくれる人もいるが、日本のコンニチハに匹敵するくらい、ヒロシマ、ナガサキは、ここでは知れ渡っている単語なのだ。
そして日本人を騙す連中は、きまって日本に友人がいるという。
当然嘘であるが、その友人が東京に住んでいると言うと、騙す相手である旅行者も東京出身の可能性が高く、つっこまれて嘘がばれる危険性があり、東京、大阪などの地名は避ける。
そして、彼らが良く知っていて、あまりバックパッカーの出身地でない地名として、広島、長崎はちょうどいいのだ。
だからムハンマドが、娘が長崎に行くと言ったとき、おやっと思ったが、それ以上気に止めなかった。
この時点で私は彼を信用しきっていた。
彼が娘の話をするときの、嬉しそうな、でれっとした顔が、私を信用させた。
私は長崎のことはわからないが、と断ってから、簡単に日本のことを説明した。
『人口は約1億2千万。
比較的内気な国民性だと言われるけど、親切な人が多い。
戦争が終わり50年以上たち、反米感情などはない。
宗教については、大半は仏教徒であるが、あくまで形式的なものでしかない。
結婚はキリスト教式であげるのが一般的だ。
国民の大部分が無宗教といっても差し支えない。
それから一応言っておくけど、日本はフリーセックスではない。
もちろん、ムスリムほど厳しくはないけどね』
セックスのことをあえて言ったのは、以前、日本はフリーセックスで羨ましいと言っていた男性に何人も会ったことがあるからだ。
一通り私が話し終わると、彼はシーシャ(水タバコ)を注文し、吸ってくれという。
彼がトライ、トライ、と薦めるので、私は何度もやったことがあると断わったが、結局はその薦めにまけて、アップル風味に煙を楽しんだ。
『そうか、やっぱり日本は人も親切で、いい所みたいだな、安心したよ』
と彼も満足そうだった。
そして今夜ルクソールに向かうという話をすると、あそこは旅行者を騙す連中が多いから気をつけてくれという。
『両替がすんでいないなら俺がいい店を紹介しようか。
ルクソールはレートがよくない』
しかし、両替は残りのエジプトの滞在日数を考え、すでに済ませていた。
サファリビルの入り口に、ヘチマを売っている老人がいて、彼の耳元で、チェンジマネーというと、奥へ連れていってくれ、両替してくれるのだ。
銀行よりもかなりレートが良く、ちょっとした名物だおやじだ。
その彼のところですでに両替はしていたが、50エジプトポンド(約1000円)の高額紙幣しか持っていなかった。
今泊まっているベニスホテルが、1泊7エジプトポンド。
国民食のコシャリが2エジプトポンド。
つまり、50エジプトポンドは、かなりの高額紙幣で、嫌がられることも多い。
それをムハンマドに伝えると、くずしてくれるという。
私は彼自身がくずしてくれるのかと思い、50エジプトポンドを渡した。
それを受け取った彼は、すくっと立ち上がり、くずしてくるといって通りに消えていってしまった。
私は、あまりに突然だったのと、彼の行動を予想もしていなかったので、引き止める言葉も出ないうちに、彼は消えていってしまった。
待っている間不安だった。
これで彼が帰ってこなかったら、私はただのお人好しである。
シーシャを吸いながらそんなことを考えていてが、10分ほどでムハンマドが帰ってきた。
『何件かの店でことわられたけど、やっとやってもらえた』
と言って、10エジプトポンド札を5枚出した。
これで私はこれでムハンマドを完璧に信用した。
『私の家はこのすぐ近くなんだが、よかったら家内とオリビアを連れてきていいか?
親の私が言うのもなんだが、オリビアはすごい美人だ。
鉄郎と一緒にみんなで記念写真をとりたいんだ』
私に断わる理由もない。
そして、ムハンマドは、
『頼むからオリビアにキスはしないでくれ』
と言う。
『日本人にそんな習慣はない』
と説明すると笑っていた。
そして彼は、オリビアを呼んでくると言い、一度家にもどり、すぐにまた現れた。
しかし、ムハンマドの娘の姿はなく、彼一人だ。
『家内もオリビアもとても喜んでいた。
日本人のフレンドができたってね。
今からシャワーを浴びて、それから化粧をしてくるから、もう少し待ってくれ』
化粧はともかく、シャワーとは大げさだが、悪い気はしない。
私もその美人だというオリビアを見てみたかった。
それに彼女たちと一緒に写真を撮るといことは、その後で私が彼女の写真を撮っても問題ないだろう。
イスラムの女性は写真を嫌う。
カメラを向けるとまず、ラー、ラーを言われる。
ノー、ノーという意味だ。
しかし、今回は思いっきり撮れるし、しかも美人ときている。
ぜひとも彼女をフィルムに収めたかった。
一緒に写真を撮った後に、彼女一人の写真を撮りたいとムハンマドに確認すると、別に問題ないという。
これはついてる。
奥さんとオリビアを待っている間、ムハンマドは、私がテーブルの上に無造作においたタバコを指差して、いくらで買ったかを聞いた。
それはクレオパトラというエジプトのタバコで、決して旨いわけではないが、最も安い。
『1.75エジプトポンド(約36円)だ』
と言うと、それならローカルプライスだという。
『でも私の友人の店で1カートン(10個入り)で、13エジプトポンドだ。
1箱1.3エジプトポンド。
どうだ安いだろう。
ルクソールは高いから、ここで買っていったほうがいい。
どうする?』
『それじゃ1カートンたのむ。
お釣りは細かいのでくれ』
と私は50エジプトポンド札を彼に渡した。
そしてムハンマドは、
『そろそろオリビアたちが来る時間だから、行こう』
と言って、席を立ち上がった。
ここに来ると思っていたので、そのことを彼に言うと、
『ここじゃまずい、わかるだろう。
カイロはムスリムの街だ。
そのカイロの路地裏のシャイ屋に女性が来るなんてことはできないんだ。
近くの公園に行こう。
そこなら大丈夫だ』
なるほど、もっともな話である。
カイロは都会であり、女性もよく出歩いているいる。
しかし、マクドナルドや喫茶店に入る女性は多いが、さすがに路地裏のシャイ屋では、女性はあまりに目立つ。
いつもシャイ屋は男性でいっぱいで、それぞれにシャイをすすったり、水タバコをふかしている。
そのなかに若い女性が入ってきて、外国人と写真を撮るというのは、あまりよろしくないというのは、私にもわかった。
ムハンマドは会計をすませた。
もちろん奢ってくれた。
そして通りに出て、公園は近いが安いからタクシーで行こうという。
タバコ屋はその公園の近くらしい。
タクシーに乗っている時間はわずかだったが、その間もモスクが見えるとその説明をしてくれたり、通りの名前を教えてくれたり、ちょっとしたガイド気取りだった。
5分ほどでタクシーを降りたが、そのときに彼が、細かいお金がないので立て替えてくれという。
私はさっき彼に両替してもらった10エジプトポンド札があったので、それを渡した。
タクシーを降りたところは、以前歩いて来た場所で見覚えがあった。
土産物屋が並び、野菜や果物を売る屋台があり、ごちゃごちゃしたマーケットになっている。
『あと5分もすれば家内とオリビアが来る。
公園はすぐそこだ。
その間にタバコを買ってくるよ。
ちょっと待っていてくれ』
ムハンマドは言い残し、車の往来の激しい道路を、すいすいと器用にわたっていった。
そして、マーケットの中に消えていった。
確か、初めてムハンマドと会ったときに、彼は片足をひきずって歩いていた。
しかし、その彼がすいすいと道路をわたっている。
これはどういうことなのだろうか。
彼が消えてから5分ほどたっても、まだムハンマドは戻ってこない。
『これで彼が帰ってこなかったら、俺もただの間抜けだ』
などと冗談半分に考えていたが、10分たった頃から不安に思ってきた。
さすがに15分たつとあせってくる。
『俺は騙されたのだろうか、しかしまだ15分じゃないか。
タバコ屋が見つからないのかもしれない。
いや、友人とばったり会って話しこんでいるのかもしれない』
と自分に言い聞かせる。
20分たった。
30分たったら諦めようと決めて、私は彼が現れることを祈った。
人が悪いといわれるエジプトだが、そうでない人だってたくさんいる。
私はそういう人と出会い、短いが貴重な時間をすごした。
そんなことを、エジプト人を頭から信用せず、そして馬鹿にする旅行者に言ってやりたかった。
しかし、時間は虚しくすぎ、30分たった。
私は彼の消えたマーケットの方へ足を運び、一応は捜してみたが、見つかるわけもない。
仕方なく宿の方向へと歩き出した。
ムハンマドに渡したお金はタバコ代と、タクシー代で、60エジプトポンドである。
日本円になおすと1250円くらいだ。
別に金額としては惜しくない。
結果からみると私が恥ずかしいほど、うかつすぎた。
しかし後味が悪い。
旅行中に人を信用することができずに、頭から疑ってかかり、最終的には彼が信頼できる人物で、こちらのことを親身に考えてくれたことがわかったときほど、嫌なものはない。
はじめから疑ってかかるのは簡単なことなのだ。
しかし、人に信頼されるのも、人を信頼するのも、なんと難しいことか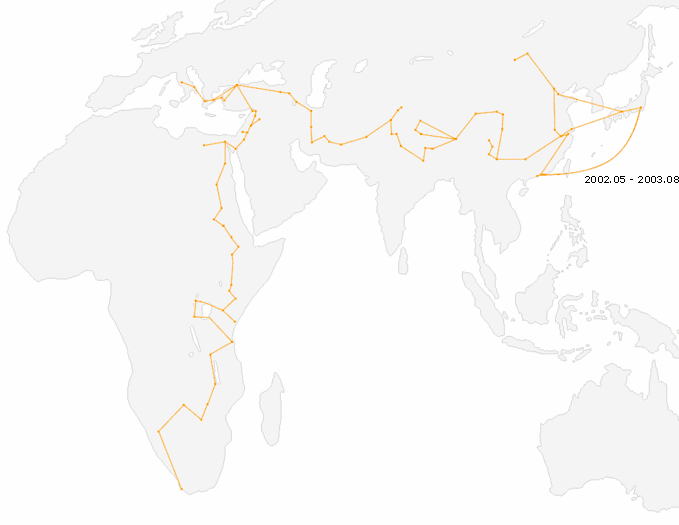 鉄郎 初めての海外旅行は22歳の時。大学を休学し半年間アジアをまわった。その時以来、バックパックを背負う旅の虜になる。2002年5月から、1年かけてアフリカの喜望峰を目指す。
鉄郎 初めての海外旅行は22歳の時。大学を休学し半年間アジアをまわった。その時以来、バックパックを背負う旅の虜になる。2002年5月から、1年かけてアフリカの喜望峰を目指す。