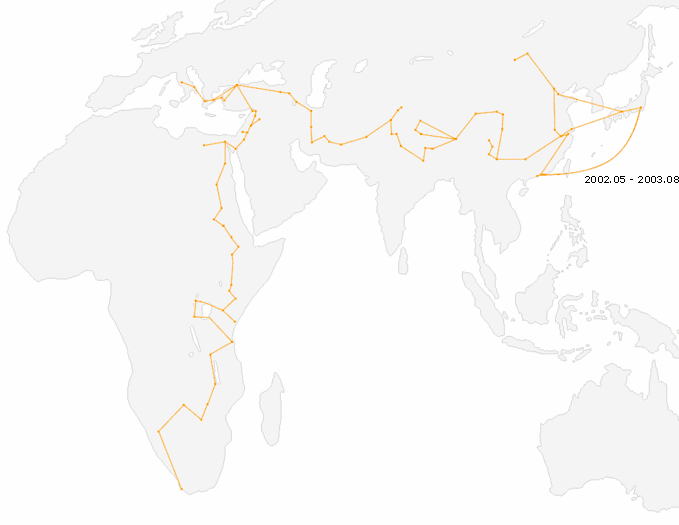イミグレーションを出て、乗合トラックで街まで行く。
そこから首都のハルツームまで列車が出ている。
私の目的地もそこだ。
列車が出るのは、次の日である。
この列車が相当つらいという話であった。
炎天下の中を列車は走るが、信じられないほど車内は暑くなる。
当然冷房はない。
1等車両でも冷房はなく、しかもベッドもないという話だ。
かといって、窓を開けると、砂漠の中を走っているので、砂が入ってきてそれもできないらしい。
そして砂にレールが埋もれ脱線も日常茶飯事。
その度に、どうやるのかは知らないが、職員が脱線をなおすらしい。
ハルツームまでうまく行って2泊3日。
遅いと3泊4日になる。
ここもムスリムの国なので、みんな到着時間はインシュアッラーだという。
アッラーだけが知っているという意味だ。
つまり何時着くか誰もわからないということである。
そんな列車にのっても話のネタくらいにしかならないので、あえて乗りたいとは思っていなかった。
とはいえ前に進むには、他に選択肢はないと諦めていた。
しかしフェリーで知り合ったスーダン人たちは、バスでハルツームまで行くという。
そう、バスという選択肢があったということを、私は初めて知った。
バス乗り場に行くと、列車が脱線するのと同じがそれ以上の確率で故障するであろうことは、そのバスの外観をみるとすぐにわかった。
とはいえ、地元の人はほとんどがバスを使っているという。
ということは、少なくとも列車よりはましなのではないだろうか。
私はバスで行くことに決めた。
バスは夜出るのでまだ時間がある。
食事を済ませて、バスの発車を待った。
バスの料金は、アトバラというハムツールまでの中継地点まで4200スーダンディナール、
ざっと1900円ほどだ。
他のスーダン人をよく観察しても、その額を払っているので、ぼられているというわけではなさそうだが、物価を考えると結構高い。
ダメもとで一応値切ってみると、すぐに4000スーダンディナールになった。
90円ほどのディスカウントだ。
しかし、それが間違いだったのかもしれない。
夕食後、7時30分くらいにバスに乗り込んだ。
日本のどんなローカルな路線でも走っていないであろうこのオンボロバスは、以外にもチケットにシートナンバーが書いてあり、どこに座ってもいいというようなものではなかった。
私は周りの人にチケットを見せ、自分の座席を確認すると、一番後ろのシートであった。
バスは左側が3列シート。
通路をはさみ右側に2列シートがある。
シートといっても限りなくベンチに近い。
クッションなんてあってないようなもので、すぐにお尻が痛くなりそうな代物だ。
背もたれは当然背中の所までしかなく、頭をもたれかける部分はない。
これがあるとなしでは、寝るときの快適さがかなり違う。
頭を固定できないと寝るのは非常に難しい。
そしてこれも当然だが足元のスペースもとても狭い。
さらに、私の割り当てられた一番後ろの席は、他の席と比べても、それよりも劣るものなのだ。
とにかく足元が狭く、だらりと浅くすわると、膝が前の席にぶつかる。
常にしっかりと深く座っていなければいけないほど狭い。
いったいこのシートはどうやって決めたのだろうか。
早いもの順であるなら、私がチケットを買ったタイミングは、決して遅くないほうであった。
だとしたら、値切ったからこのシートになったとしか考えられない。
値切るくせがついていると、こんな目に遭うこともある。
たかだか90円のために、このあと20時間、このスペースでひたすら耐えなければならないことになる。
こんなことならば4200スーダンディナール払って、普通のシートにすればよかった。
8時すぎにやっとバスは走り出した。
シートは全て埋まり、通路にはズタ袋やらダンボールやらで一杯になり、その間に立っている乗客もいて、山手線のラッシュアワーに近いものがある。
灯りなど一つもない完璧な砂漠の闇をバスは走った。
真っ暗なので、よくはわからなかったが、思いのほかスピードを出しているようだった。
『これならば、列車よりは早く着くだろう。』
自分の選択が正しかったと確信が持てたのは、わずか数分であった。
その思いはすぐに疑問に変わった。
砂漠のなかに舗装された道路などあるわけもない。
ただ、本当に純粋な砂を上を走っているのだ。
それも明かりなど一つもない、完璧な夜の闇を走っている。
砂漠の砂にも、盛り上がっているところもあれば、凹んでいる部分もある。
そこを通過するたびにバスは跳んだ。
揺れたとかそういう感覚ではなく、跳ぶのだ。
とうぜん、そういったバスの振動は乗客にもつたわってくる。
バスが跳ぶたびに、私の体もまた中に浮く。
そしてバスが着地して、その後、私もまた着地する。
その度に内臓をうちつけらるような感覚を受ける。
私は必死につかまりながら、耐えているが、他の乗客は案外平気だ。
別に慣れているというわけではない。
車の跳ねというのは、後方に行くに従ってひどくなる。
前方の乗客は案外平気なのだ。
私のシートは最後列である。
私はたかが90円を値切った自分を恨んだ。
跳ねる前に、もっとスピードを緩めてくれればいいのにと思うが、そうはいかないらしい。
ここは砂漠の中だ。
スピードを緩めればたちまち砂にタイヤをとられ、スタックしてしまう。
つまりは、ジャンプしようが、振動がひどかろうが、私の内臓が痛くなろうが、そんなことはお構いなしに突っ走るしかないのだ。
私はこのバスを「ジャンピングバス」と呼ぶことにした。
とはいえ、いかにジャンピングバスがジャンプして走っても、砂にタイヤと取られ、スタックすることはめずらしくない。
バスのタイヤが砂に埋まり、発進できなくなると、屋根にいた二人の男がバス後方の梯子から素早く降りてくる。
いったい彼らはこの悪路で、どうやったら振り落とされないで、バスの屋根に乗っていられるのだろうか。
そしてその梯子にはさんである、直径10センチくらいの2本の丸太を引き抜く。
長さは3メートルほどはある。
それを砂に埋めるように、スタックしているタイヤに噛ませる。
しかし、それで脱出できるとは限らないから、彼らはまだそこにいる。
そしてドライバーが一気にアクセルを踏み込み急発進する。
タイヤが丸太を踏むときに、ガタン、ガタンという振動があり、バスが発進する。
驚いたのはそれからだった。
せっかくうまく発進できたのに、その丸太の男たちを待つために、バスが止まると、またスタックする恐れがある。
だからバスはそのまま走り続ける。
その瞬間、二人の男は素早く丸太を拾い、走ってバスに追いつき、もとあった梯子のところに丸太をひっかけ、そしてバスにしがみつき、また屋根に登っていく。
職人技だ。
そしてバスは砂漠の闇を、また走り続ける。
このバスは一応夜行バスではあるが、そんなことが続くから、寝ることなんて不可能だ。
数分眠ったかと思うと、また例のジャンプで起こされる。
明け方、まだ暗いうちに、ある村で休憩し、チャイとビスケットを食べた。
食べている間に夜が明けた。
砂漠に昇る朝日というのは初めて見たが、何もないシンプルな美しさがある。
しかし、ここからが、また別の苦難の始まりだった。
砂漠は日差しが強い。
つきささるようだ。
日が昇るにつれ、気温はぐんぐん上がる。
息苦しいくらいだ。
温度計をもっていたので、見てみると、なんと45度だった。
車内は蒸し風呂みたいになり、窓を開ける。
それで気温が下がるわけではないのだが、風が入ってきて、少しは暑さがやわらぐ。
しかし、そうすると、バスの前輪で舞い上がった砂が、窓から吹き込んでくる。
5分もすると、まるでスライディングした高校野球児みたいになる。
髪の毛もまるで1ヶ月洗っていないような色になり、顔を触っても砂でざらざらす
る。
服は言うまでもなく、ちょっとたたいただけで、砂が舞い上がる。
窓を開ければ、風は入るが、一緒に砂も入る。
閉めればサウナ状態である。
どちらもつらい。
私としてはもう、一度砂だらけになってしまえば、もう関係ないので、窓を開けたかったが、現地の人たちは、暑さに慣れているらしく、すぐに窓を閉めたがった。
私の近くの窓では、私が開け、またしばらくすると、現地の人が閉め、また私が開けるということを繰り返している。
この暑さでは、当然咽が渇いている。
用意していた1リットルの水もすでに飲んでしまった。
こんなバスでも水の支給のサービスがある。
しかし、それはペットボトルの水なんかではなく、バケツでまわってくるのだ。
現地の人は、それについているコップでゴクゴクと飲む。
しかも、凍らせている状態でバスに積み込み、それが溶け出したところで飲むので、
実に冷えていて、うまそうだ。
『これはナイルの水だ。まずいわけはないだろう』
と誰もが言う。
ナイル川の水を、そのまますくってきたという。
そんな水が果たして私に飲めるのだろうか。
私は、自分の水があるうちは、どんなに薦められても、ナイルの水は遠慮した。
しかし、45度の暑さで自分の水はすぐになくなり、咽の乾きには勝てない。
ナイルの水で病気になるのも怖いが、このまま水を我慢して脱水症状になるのも怖い。
『えーい、ままよ』
とそのバケツのナイルの水を飲んでみる。
とにかく冷えている。
味は、うまい。
少し飲んでも、大量に飲んでも、病気になるときはなるのだと割り切って、何杯もおかわりしてしまった。
結局その水で腹を壊すことさえなかったが。
振動と熱気の苦痛は、その後も続いた。
それは移動というより、ただ耐えているというだけのものだった。
もちろん一睡もできない。
そしてバスが出発してから20時間後、やっとアトバラに着く。
そこで1泊し、次の日バスを乗り換えハルツームに着いた。
アトバラからハルツームは、道路が舗装されていた。
旅をして、辺境の地などに行き、道路が舗装されていると、勝手な話しではあるが、なんとなくイメージと違い少しがっかりしたりするが、このときほどアスファルトの道路をありがたく思ったことはない。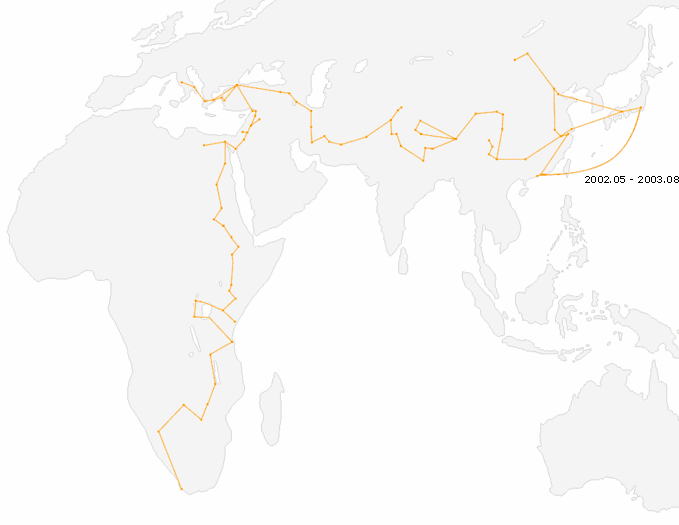 鉄郎 初めての海外旅行は22歳の時。大学を休学し半年間アジアをまわった。その時以来、バックパックを背負う旅の虜になる。2002年5月から、1年かけてアフリカの喜望峰を目指す。
鉄郎 初めての海外旅行は22歳の時。大学を休学し半年間アジアをまわった。その時以来、バックパックを背負う旅の虜になる。2002年5月から、1年かけてアフリカの喜望峰を目指す。