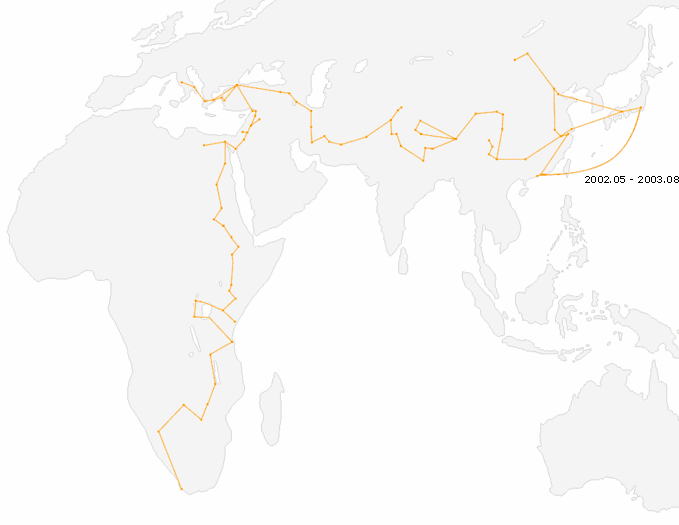少し坂になったその道をちょっと行くと右手に低い門と柵があって、そこにアルファベットで「クリシュナ・ゲストハウス」と書かれている。門の内側には小さな庭があり、L字型になった二階建ての建物は明るいベージュ色に塗られていて、見た感じは小ざっぱりとして、悪くはなかった。正面にいくつか見られる緑色の木の扉には番号が記されており、そこが宿泊用の部屋だということを表している。庭に生えている二本の木の間にはハンモックが吊るされており、それが風で少し揺れている。ひっそりとしていて人気はない。
「心路、本当にここなんだよな? 誰もいる気配がしないぞ」
「確かにここだよ。多分中にいるんじゃないのかな? この間来たときもこんな感じだったし」
「本当かよ? ところで今何時?」
直規は、心路にそう尋ねると、心路は、時計持ってない、という風に首を振ったので、すかさず智の方を振り返った。智は、それに気が付くと腕時計を見て、八時四十分、と言った。
「ちょっと遅くなったかな」
「大丈夫だよ」
心路は、気に留める様子もなくそう言うと、柵を開けてずかずかと中へ入っていった。
そしてゲストハウスの入り口の扉の前まで来ると、二三回軽くノックした。返事は無い。
「いないのかな?」
少し緊張して智がそう言った。しかし扉の隙間から漏れてくる光で、中に灯りのついていることは分かる。
「いや、灯りがついているから多分いるとは思うんだけど……」
そう言うと心路は、続けざまにまた何回かノックした。しかし何の応答もない。扉をノックする音が静まり返った空間に響き渡るだけだった。
「やっぱり時間間違えたんじゃねぇの?」
直規が、責めるように心路にそう言った。
「いや、そんなことはないと思うよ、確かにあいつ八時って言ってたよ」
「じゃあ、俺らが遅かったからどっかに行っちまったっていうのか?」
「分かんないよ」
二人の言い合いが発展しそうになるのを見かねて智が割って入った。
「ちょっと待ってよ、今、そんな言い合いしたってしょうがないだろ?」
二人は、智のその言葉に少し冷静になってお互いを見返した。
「どう、出直す?」
と、智が言ったその時、二階の部屋の一つに灯りがついて誰かが出て来るのが見えた。
暗くて良く分からないがインド人らしく、彼は、三人の様子を二階から眺めながら英語で、どうしたんだ、何か用か、と尋ねてきた。それに気付いた直規が、シバに会いに来たんだが、と答えると彼は、ああ分かったちょっとそこで待ってろ、と言って部屋の中に姿を消した。
しばらくすると三人の目の前の扉の向こうから足音が近付いてきて、ガチャガチャと鍵を開ける音がした。そしてスーッと扉がゆっくり開くと、タンクトップシャツを着た筋肉質の若いインド人が姿を現し、入れ、と行って首を傾げた。髪は、ヘア・オイルでねっとりと撫でつけられている。直規は、横目で彼を見ながら頷いて、心路に、こいつがシバか?、と日本語で尋ねた。心路は、いいや、と首を振るとそのタンクトップ姿のインド人は、シバという名前で会話を察したらしく、シバはもうすぐ帰ってくるからちょっとこっちで待っててくれ、と三人を二階の部屋へと案内した。
階段を上って連れて行かれたその部屋は、先程その男が出てきた部屋で、どうも客室のようだった。ベッドが一つに木の扉のついた小さな窓が一つ、部屋の壁は、外と同じく明るいベージュで塗られており、さらに壁一面にペンキか何かでカラフルな絵が描かれていた。それらはデフォルメされたヒンドゥーの神々だった。後はゆったりとした籐製の背もたれ椅子が一つと小さなテーブルが一つ、電気スタンドが一つ、その他には何もない。典型的な安宿の一部屋だ。様々な日用品が辺りに雑然と並べられているのを見ると、どうやらタンクトップはここで生活しているようだった。
彼は、部屋に入るとベッドの上に腰掛けた。そしてそれに向かい合うように直規は籐椅子に座り、心路と智は座る所が無いので仕方なく、床に座った。
タンクトップは煙草を取り出すとマッチで火をつけ深々と煙を吸い込んだ。それに釣られて直規も煙草に火をつけた。
「ヒンドゥー・ゴッズ」
壁に描かれた絵を眺めていた智を見て、インド人はそう言った。
「あなたが書いたの?」
智がそう聞くと、そうだ、と言って何度も得意気に頷いた。
「シバはいつ帰ってくるんだよ?」
テーブルの上の灰皿を床に座る心路の前に置きながら直規は尋ねた。心路は、横目で直規に礼を言って煙草に火をつけた。
「ああ、もう帰ってくる。今ネタを取りに行ってるんだ。すぐ帰ってくるよ」
タンクトップは、二人のその様子を眺めながら窓の外にせわしなく煙草の灰を落としている。
「ここで働いてるの?」
智が彼に尋ねた。
「ああ、そうだ、シバと一緒にここで働いている」
「ここのゲストハウス、泊まってる人いる? 何だかシーンとしてるけど」
「いるよ、向こうの部屋に二組と下の部屋に一人、イギリス人の二人組とイスラエル人とフランス人のカップル、あとはドイツ人の五人かな」
「でも、誰もいないみたいだけど……」
「今、みんな出かけてるんだ」
「出かけるってどこへ? 町に出たってどこも閉まってるし……」
「知らないのか? 今日はパーティがあるんだよ」
それを聞いた直規と心路は、その瞬間、顔を見合わせた。
「知ってた? 心路?」
心路は、いいやというように首を振った。
「どこでだよ?」
直規が尋ねた。
「町から少し行った所だ。よくパーティ会場になってる小高い丘のような所があって、そこでやってるんだよ」
「行ってみる? 直規君」
心路がそう尋ねると、直規は、ああそうだな、帰りに行ってみようか、と言いながら体を屈めて、床の上に置かれた灰皿で煙草の火を揉み消した、と、その時、外で柵の開く音がするのが聞こえた。屈んだ姿勢のまま直規が顔を上げると、タンクトップは、窓から外を覗いて、シバだよ、帰ってきた、と言った。智は、少し緊張して直規達の方を振り返ると、二人はとても嬉しそうに微笑んでいた。わくわくしているようだった。やがて階段を上る音が聞こえてきて、シバが姿を現わした。