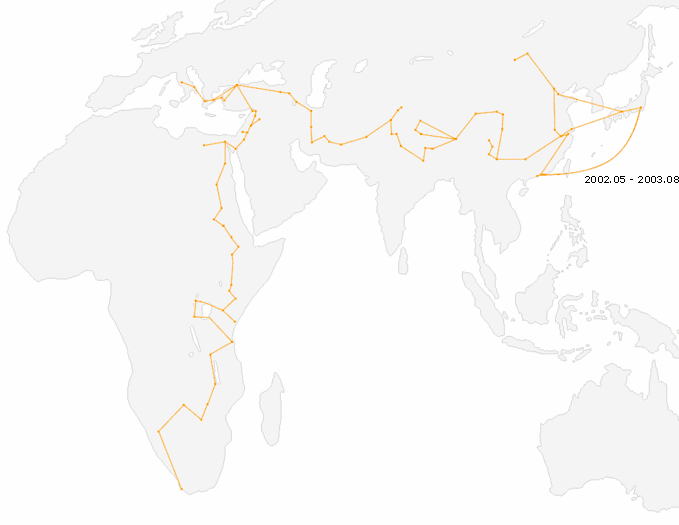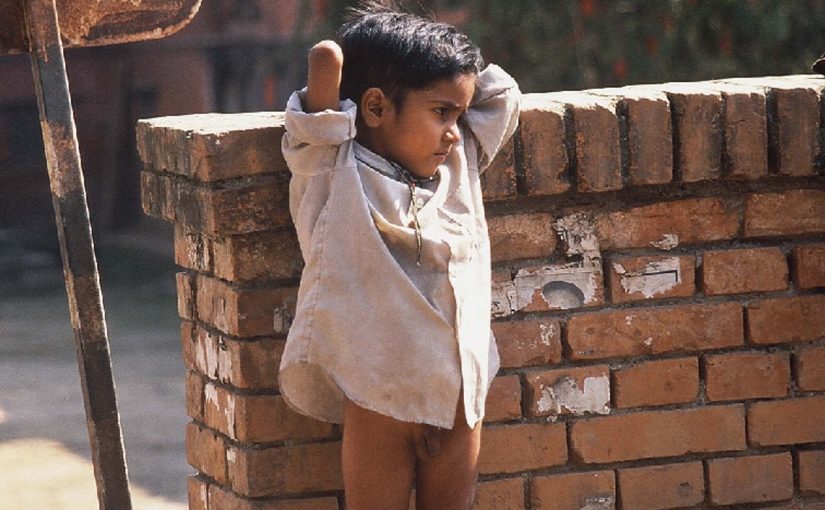その日、いつものように私は目を覚ました。
この時点では別にいつもと変わらない朝だ。
私のいる場所はヨルダンの首都アンマンにある、クリフホテルというところだった。
中東の安宿のなかでも、最も有名な安宿の一つである。
こんな状況でも客は多い。
日本人が多くて、10人以上はいた。
部屋を出てロビーに行くと、従業員のサミールが掃除の手を休めて、テレビを見てい た。
痩せていてメガネをかけた、30代半ばに見える彼は物腰が低く、見るからに、いい人という印象を受ける。
彼の評判はよく、「中東一のホテルマン」と言われている。
もちろん、それは安宿の中での話でのことではあるが、実際そうだと思う。
安さだけが売りの安宿のなかで、なるべく良いサービスを提供しようという気持ちが伝わってくる。
彼のおかげで、宿の中はいつも比較的清潔だし、旅の相談にものってくれる。
フレンドリーであるが、かといってべったりとしたところもなく、日本人にはうけるタイプだろう。
その彼がため息にも似た声で言った。
『始まったよ』
という短い言葉で全てはわかった。
始まったのは戦争だった。
アメリカによる、イラクの攻撃が始まったのだった。
イラクはこのヨルダンの隣である。
つまりは、そんな状況なのだ。
アメリカが国連の決議なしで、イラクを攻撃するであろうことは、わかりきったことだった。
いくら旅行中とはいえ、場所が場所だけに、毎日インターネットでニュースをチェックしている。
それを読めば、それくらいのことはわかる。
だから戦争の開始は別に驚きはしなかった。
それはサミールも同じだろう。
しかし他のアラブ諸国の人たちと同様に、私にとってもアメリカの正当性というものはとても受け入れられるものではなかった。
もちろんサミールにとってはなおさらだろう。
日本人としての私は、日本がアメリカ支持を表明しているので、肩身が狭い。
しかし、多くの日本人が心からアメリカを支持している、というわけではないことは、ここにいてもわかった。
かといって、積極的に反対するわけでない。
もちろん全ての日本人がそうだとは思わないが、多くの日本人が、遠い国の出来事としか感じていないのではないだろうか。
一般の人にとっては、イラク問題よりも、自分の給料や恋人との問題のほうが重大である。
それが普通の感覚だ。
そうはいっても、ここへ来れば、アメリカを支持している日本人になってしまう。
もちろん私にそんなつもりはなくてもだ。
外から見れば、私でさえ日本を背負って立つことになってしまう。
前回の湾岸戦争のとき、私は高校3年生だった。
開戦の日、私はニュースが見たくて、学校を休んだ。
時期としては受験の直前だったので、
『家で勉強します』
と言えば、学校側も何も言わなかった。
その時の、戦争の印象を正直に書けば、それはいかにもゲーム的であった。
当時の私にとって、国際情勢などわかるわけもなく、また人並み以上の興味があったわけではない。
ただ、アメリカという正義の味方が、イラクという悪を退治しているように思えた。
スカッドミサイルやピンポイント攻撃の映像は、いかにもゲーム的であった。
そう思ったのは、まだ私が幼かったからというよりは、日本から遠い国の出来事であったからだと思う。
つまり、自分の日常とは全く無関係の出来事であるから、そうやって無責任にニュースを見られたのだろう。
その頃の私にとっては、どうやったら彼女ができるかや、受験のことのほうが、よっぽど重大事だった。
しかし、今回は違う。
すぐ隣の国で戦争をやっているのだ。
アンマンの街はいつもと同じように動いていた。
人々はいつもと同じように仕事についている。
サミールもそうだ。
路上で売られる新聞には、でかでかと空爆の様子や、フセインやブッシュの写真を載せている。
アンマンでも反米デモがあったらしいが、効か不幸かそれに出くわすことはなかった。
しかし至るところで、
『何故日本はアメリカの味方をするんだ』
と聞かれる。
それは、入った食堂であったり、コーヒー屋であったり、道端で突然聞かれたりもする。
最初の何回かは、
『日本はアメリカと同盟をしているし、北朝鮮の脅威がある以上、アメリカと事を構えるわけにはいかないんだ。
しかし個人的には今回の攻撃には賛成できない』
ともっともらしいことを答えていたが、そのうちにそれも面倒になってやめた。
彼らにとっても、日本と北朝鮮の問題はやはり遠すぎるようだった。
韓国は知っていても、北朝鮮を知らない人さえいた。
そのうちに私は、
『アメリカ人は嫌いではないが、アメリカ政府は嫌いだ』
と答えることにした。
たいていは、それで丸く収まる。
宿の近くにイラク料理屋があった。
いくつかのスープのなかから、一つ選び、それをライスにかけて食べる。
他にはチキンやマトンのケバブなどもあった。
料理そのものは、このあたりとそれほど変わらないように思えたが、安くて旨い飯を提供してくれるので、よく足を運んだ。
戦争がはじまってもいつものように営業していた。
当然、従業員はイラク人だったし、客もイラク人が多かった。
あるとき、客の一人と今回の戦争について話したことがあった。
彼は私より、一回り上の年齢に見えた。
しかし、アラブの男性は、その髭のせいか、年齢よりも老けて見えるから、同じくらいの歳かもしれない。
その彼は、それなりのインテリらしく、英語を使った。
他の客が英語をわからないためか、彼はよく喋った。
『フセインはイラクの独裁者だ。
しかし、ブッシュもまた、独裁者になろうとしている。
二人は似たもの同士だな。
俺はフセインが嫌いだが、かといって、ブッシュが好きなわけでもない。
アラブのことはアラブが決める。
イラクのことはイラクが決めるのが一番いいんだ』
と彼は言った。
彼の意見は多くのイラク人を代表するものではないと思えたが、私は、隣りの国が今確かに戦争をしているということ、を感じないわけにはいられなかった。
いろんな人がいて、いろんな考えがある。
イラクもまた一くくりで語れるわけもない。
『日本は原爆を落とされたのに、どうして、アメリカの味方をしているんだ?』
やはり彼は聞いてきた。
私はとっさに答えられなかった。
原爆を落とされた時、当然私は生まれていない。
日本で生活していたって、原爆なんて単語は、毎年の8月を除けば、めったに聞かない。
私にとってのアメリカは、原爆を落としたアメリカではなく、ただのアメリカでしかない。
日本についても、韓国、台湾を占領し、中国に満州国を建てた日本ではなく、経済成長を遂げ、豊かになった日本でしかない。
『とにかく早く平和が来ることを祈るよ、それが私の意見だ』
私は彼にあたりさわりのないことしか言えなかった。
自分の知識のなさが嫌になってくる。
ここにいると、個人的な意見はともかく、やはりアメリカを支持する日本人として、見られてしまう。
それは避けられない。
幸いそれで嫌な思いをしたことはないが、自分が歴史の渦のなかにいることに、変わりはなかった。
確かに私は歴史の流れの真っ只中にいる。
そう一番に感じたのは、意外ではあるが、自分の宿の中だあった。
あるとき、紺色のスーツ姿の東洋の青年が、私のいる安宿を訪ねてきた。
こぎれいではあるが、やはり安宿である。
そこにスーツという姿が、いかにも不釣合いであった。
彼はロビーにいた私にまず話しかけてきた。
『旅行ですか?』
日本語だった。
『ええそうです』
と答えた私に彼は続けた。
『イラクに行く予定はありませんか?』
『戦争をやっている国になんて行きませんよ』
『そうですか。よかった』
と彼は少し笑い安心した表情になった。
いかにも真面目という顔が、笑うと途端にとっつきやすい顔に変わる。
『えーっと、あなたは・・・』
と私が聞くと、
『失礼しました。
私は日本大使館の職員なんです。
イラクへ行こうとする旅行者を説得しに来ているんです』
と彼が答える。
外務省というと、あまり良いイメージは持っていないが、彼には好感が持てた。
『そんなにいるんですか?イラク行きが。』
『だから困っているんですよ。
もう面倒見切れなくて』
イラクへ行くとすれば、この通常このヨルダンのアンマンが基点となる。
戦争の数週間前までは、イラク行きのツアーがこの宿から出ていた。
内容はメソポタミア文明の遺跡見学らしい。
戦争の3週間ほど前までは、5人集まればツアーが出ていた。
しかし、そのツアーもさすがに現在はない。
とはいえ今もイラクに行こうとしている人がいるのは知っていた。
彼らが見たいものはもちろん遺跡ではない。
以前は取るのが困難であったイラクビザだが、今では日本大使館のレターも必要なく、簡単に出るらしい。
イラク大使館へ行き、
『ヒューマンシールドに参加する』
と言えば、その場でもらえるという話だった。
ヒューマンシールドはイラクにとっては、いざというときに人質に使える。
だから一人でも多いほうがいいのだ。
またネットのニュースによれば、数人の報道以外の邦人が、未だイラク国内にいるらしかった。
たった一人で戦争を止めると言って数日前にイラクに入国した日本人もいると聞いた。
この宿にも、イラクに行くと断言している青年もいた。
実際に単独でイラクに入国しようとしたが、国境からの交通手段がなく、引き返してきたという人にも会った。
彼らの目的はよくいえば、不当な戦争を目の前にして、何かせずにはいられないといったものだ。
かといって、脱出のルートがあるわけでもなく、アラビア語ができるわけでもなく、英語も心もとない。
私から見れば無謀だ。
開戦の直前にイラクからもどってきた大学生もいた。
彼は一週間ほどイラクに滞在して、戻ってきたところだった。
もちろん彼は報道の関係者でもなければ、ジャーナリズムに関心があるわけではなく、またヒューマンシールドでもない。
中東関係の大学サークルの所属する普通の大学生である。
一度だけ、彼と話したことがあった。
私がバグダッドの様子を聞くと、
『普通でしたよ』
の一言だけで、話は終わってしまった。
街は機能しているのか。
流通はどうなのか。
食料は行き届いているのか。
交通は。
電話回線などの外部の連絡は。
雰囲気は。
国民の気持ちは。
知りたいことは山ほどあったが、その一言でその気持ちが失せてしまった。
いったい彼は何を見てきたのだろうかと、少し意地悪く思ってしまう。
普通であるわけはないと思う。
仮に、本当に普通であると思ったのであれば、感じる能力が欠如しているのではないかとさえ思った。
その学生は再びイラクに入ることを考えているらしく、大使館の職員も彼のことを知っていて、手を焼いているらしかった。
大使館の職員は、
『とにかくイラクに行くという人がいたら、やめるように言っておいてください』
と言い残して帰って行った。
外務省に強制力はないから、地道に説得するしか手段はない。
開戦の日の夜、日本のテレビ局のスタッフが、宿に来ていた。
イラク国内でヒューマンシールドを取材していたが、開戦と同時にヨルダンに引き上げてきたらしい。
そして、ロビーでイラク帰りの学生を取材していた。
それがどんな内容であったのかはわからないし、果たしてそのVTRが日本のニュースで流れたのもかもわからない。
その学生がどんな目的でイラクに行ったのかはわからないが、私には彼の行動がよくわからなかった。
私自身はやはり今回の戦争について思うことも多いし、イラクの状況には興味はある。
しかし、旅を続けることが目的なので、イラクに行こうとは思ったことはない。
そこに生命の危険を冒してまで行く目的が、私になかった。
そして、その学生を含め、これからイラクに入ろうとしている人たちからも、それは伝わってこなかった。
ただ、今のイラクに入りたい、ということ以外何も伝わってこなかった。
何かを感じたいとか、何かを伝えたいとか、そういったものが彼らからは見えてこなかった。