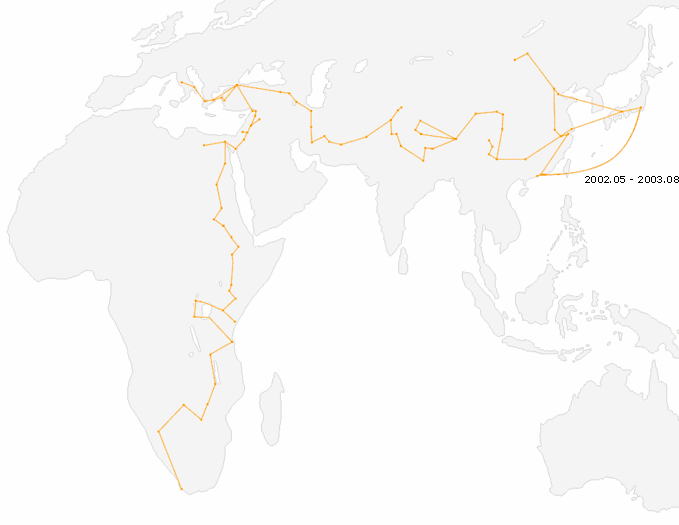このエッセイで何度か書いたことがあるが、私の旅にはカメラが欠かせない。
基本的にはいつもカメラを持ち歩いている。
旅のルートを決めるのにも、面白い写真が撮れそうだからその場所へ行く、ということもあるし、逆に写真は禁止されているから行かなかったという場所さえある。
他の人から見れば理解できない部分もあるだろうが、私にはそういうところがある。
さて、ケニアの後、喜望峰までのメインルートはそのまま真っ直ぐに南下しタンザニアと入るルートである。
しかし私はケニアの西、ウガンダへと行くことにした。
その理由は写真である。
コンゴ、ウガンダ周辺にはピグミー族が暮らしているらしい。
コンゴには治安の問題があり、ビザが下りるかどうか不安定な状態で、入れたとしても入域できない場所が多い。
しかしウガンダであれば、比較的簡単に、そのピグミー族に会えるらしい。
ピグミー族の写真を撮る。
それがウガンダへ行く理由である。
私はどちらかというと、風景より人物の写真が好きだ。
なかでも宗教的な匂いのする街に暮らす人々や、少数民族には興味がある。
ピグミー族については、どこに行けば会えるかということは、もちろん調べていたが、民族的なものについては何も知らなかった。
背が一般よりもだいぶ小さく、そして森を住みかにしている、ということくらいしか知らない。
『森の人』と呼ばれる彼らである。
その響きだけで、十分に写真を撮りに行く価値はあると思った。
ケニアのナイロビからウガンダの首都であるカンパラまでは、直通の夜行バスが走っていている。
私はケニアを後にして、ウガンダのカンパラを目指した。
カンパラの後はバスを乗り換えて、ピグミーの暮らフォート・ポータルというところへやってきた。
カンパラも首都にしてはずいぶん小さいが、フォーと・ポータルというところまで来ると、いわゆる田舎街という感じである。
そしてそこを拠点に日帰りでピグミーに会いに行くのである。
ウガンダの目的はピグミー族だけだったので、フォート・ポータルに着いた翌日、私はさっそく彼らを訪ねてみた。
彼らはフォート・ポータルから車で3時間の、セムリキバレー国立公園のなかに住んでいる。
そこまでの移動手段は乗合トラックだった。
トラックといっても、トヨタのランクルピックアップである。
そこに荷台に乗るわけだが、未舗装の道路でスピード出すので、はっきりいってジェットコースターよりも怖かった。
いくつかの山を抜け、セムリキバレーに着くと、そこには小さな村がある。
ここには一般の村人が暮らしていて、牧畜や農耕で生計をたてているようだった。
まずはそこの公園事務所へと行き、ピグミーに会う手配をしてもらう。
本来、そのまま勝手に人に場所を聞きながら歩いていけば、すぐにピグミーに会えるらしいが、ピックアップが公園事務所の目の前で私を降ろしてくれたので、それはで
きなかったし、なによりに国立公園の入園料をちょろまかすことになるので、あまり褒められた行為でもない。
事務所にはいくつかのツアーが用意されていて、トレッキングなんかもあった。
しかし1999年にイギリスの観光客8人が反政府ゲリラの誘拐され殺害されるという事件が、ウガンダ西部、つまりここからそう遠くないところであったらしく、ほとんど観光客は来ないようだった。
私が事務所の職員にピグミーに会いたいと言うと、まず公園の入園料10USドルと、ガイド量として、5000ウガンダシリング(約2,5ドル)かかるということだった。
これらは料金表にて書いてある正当な料金であるので、私は素直に払った。
そして一つ確認した。
ピグミーの写真を撮ったとき、彼らにその料金を請求されるのかどうかだ。
すると職員はそのお金は国立公園の入園料に入っているから、これ以上お金を払うことはないと言った。
そして職員がピグミーのところへと案内してくれた。
森の中を歩くものだと思っていたが、道にそって5分もあるけば着いてしまった。
これなら確かに公園事務局を通さなくても一人でこれそうだ。
『彼らがピグミーだ。そして彼が村長』
と職員が言い、紹介された男を見て私はあまりに驚いて、唖然とした。
その男の年齢は50歳くらいに見えた。
そして背が小さい。
150センチくらいであろうか。
やはり、民族的には背が低いのだ。
そして彼が着ている服装は、アルファベットのプリントの入ったTシャツにジーンズだ。
かれのまわりにいる大人たちや、子供もおなじような格好だ。
汚れてはいるが、基本的には同じような格好をしている。
アメリカのロックミューシャンのTシャツを着ている若者もいた。
女性は一般のアフリカ人と同じくスカートである。
暮らしぶりを説明してもらうと、昔は狩猟採集生活が主だったが、今はトウモロコシなどの農耕をやっているらしい。
猿を狩って食べるという習慣も今はほとんどない。
家は、以前は藁でつくったテントのような家だったが、今は土か木を張り合わせたような家に住んでいる。
自転車を持っている人もいた。
この分じゃ、ラジカセくらいな持っている人もいるだろう。
正直、期待は大きくはずれ、想像と大きくかけはなれていた。
『彼らがピグミーだ』
という説明を受けないかぎり、絶対にそのことに気付かない。
森の中をさっそうと歩くピグミー族というのは、ここにはいなかった。
しかしそのことをあれこれいう資格は私たちにはない。
この現代で伝統の文化、習慣、暮らしを守ることは、やはり相当に難しい。
日本人だってマゲと日本刀を捨て、今に至るのだから。
でもせっかく来たのだからと思い、写真を撮らせてほしいと申しでた。
記念写真みたいなものになってしまうが、それもまたいいだろうと思ったのだ。
そのことを、職員が村長に伝えてくれたが、村長からは驚くべき答えが返ってきた。
『1枚につき10,000ウガンダシリング(5USドル)だ』というのだ。
これにはあきれて物も言えなかった。
まず、国立公園の入園料に写真代は入っているはずだ。
仮にそれをさしひいても、やはり納得がいかない。
もし彼らが、観光で収入を得るために、民族的な衣装をつけ、伝統的な暮らしをしているのであれば、写真を撮られることで、お金を請求するのであればまだ納得もいく。
それにしたって、写真1枚につき5ドルという金額はどうかと思うが。
タイの首長族やケニアのマサイ族のなかには観光をその生業に選んだ人たちもいる。
彼らはきちんと定額の入村料を決め、そして英語の話せるものが、村の暮らしや、伝承など、独自の文化について説明してくれる。
写真を撮ってもそれ以上のお金を取られることはない。
首長族にいたっては、
『村の子供たちには教育上、お金や物をあげないでください。
もしそういった気持ちがあるのなら、学校や病院をたてるための費用を寄付してください』
と説明された。
ここにはそういうものはまったくない。
肖像権というものがあるので、写真を撮られたくないというのならわかる。
しかし彼らは、写真は撮ってくれ、そしてお金を落としていってくれというわけだ。
つまりはピグミー族として、紹介するべき文化や伝統はなくなってしまったが、とにかく金だけはおいていってくれということになる。
私は相当に腹がたち、村長に文句を言ったら、金額が3分の1になった。
しかし、私にとっては金が問題ではないので、写真は1枚も撮らなかった。
すると村長は、
『こないだ来たイギリス人は20ドルくれたよ。
やっぱりイギリスはいいな』
と言う。
私はますます腹がたった。
『金を持ってくる奴が好きなのか。
そうだろうよ、俺は金がないからな。
だったら一生イギリスに媚ながら生きていけばいいさ』
と思わず強い口調で言ってしまった。
世界には少数民族と呼ばれる人たちが多数いる。
彼らのなかには、観光を主な収入として暮らす人たちもいる。
そういうところには、やはり観光客が多く行くが、なかには、
『あそこの民族は観光化しているよ。
本物じゃないな』
などと、無責任なことを言う旅行者だっているが、私はそうは思わない。
民族というものは、もともと民族単位で暮らしていたのだ。
それが第二次大戦後大きく国境がかわり、あるいは新たに国境がひかれる。
そして知らぬ間にどこかの国に属すことになる。
いままではのんびりと民族単位の暮らしが、ある日突然、あなた○○国の国民になりましたよ、ということになる。
そして流通は大きく変わり、その国の貨幣がないとなにも買えない状況になり、大きな街へ行けば聞いたこともない国の製品が出回っている。
そんなふうに大きく世界が変貌した現代で、伝統や文化を守っていくということはどんなに難しいものかは、自分の国の歴史を少し振り返っただけでも容易に想像がつく。
そんななか、安定した観光収入の道を選ぶことは、何も恥じることではないと思っている。
それを選ぶことで、子供らは学校へ行き教育を受けることができ、生活が安定し、まして自分たちの生活、文化、習慣、伝統を守れるのなら、なおさらだ。
一方、伝統的な生活を捨て、街へ出稼ぎに行って、そういう昔の生活スタイルをまるっきり捨ててしまった民族だって多くいたはずだ。
大雑把に言えば、日本だって、欧米列強に負けない近代国家になるために、いろいろな伝統を捨てた。
それはそれでいいと思っている。
計画的な援助というものは必要だと思う。
しかし、何もせずに、ピグミーだといういわば中身の伴わないブランド名だけで、あわよくば収入を得ようとする彼らはどうなのだろうか。
そのイギリス人のように、ただ気まぐれに金を渡す人がいるから、ピグミーも、外国人は金をくれると思ってしまったのだとは思うが、それはとても悲しいことだ。
森の中をさっそうと歩く、誇り高きピグミーは、まだコンゴにはいるのだろうか。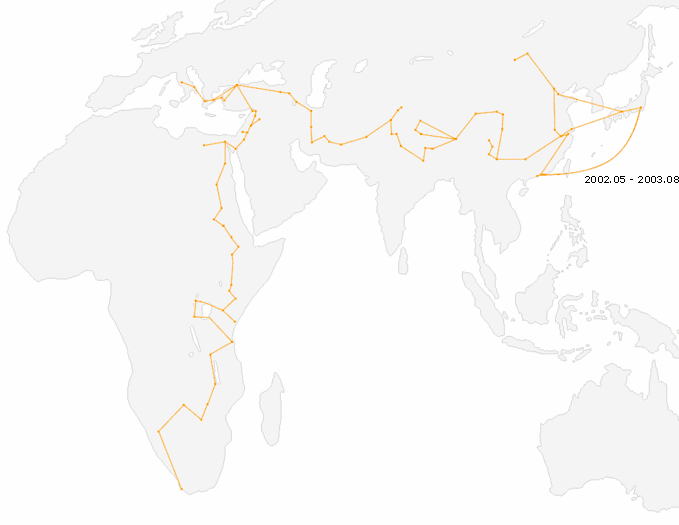 鉄郎 初めての海外旅行は22歳の時。大学を休学し半年間アジアをまわった。その時以来、バックパックを背負う旅の虜になる。2002年5月から、1年かけてアフリカの喜望峰を目指す。
鉄郎 初めての海外旅行は22歳の時。大学を休学し半年間アジアをまわった。その時以来、バックパックを背負う旅の虜になる。2002年5月から、1年かけてアフリカの喜望峰を目指す。