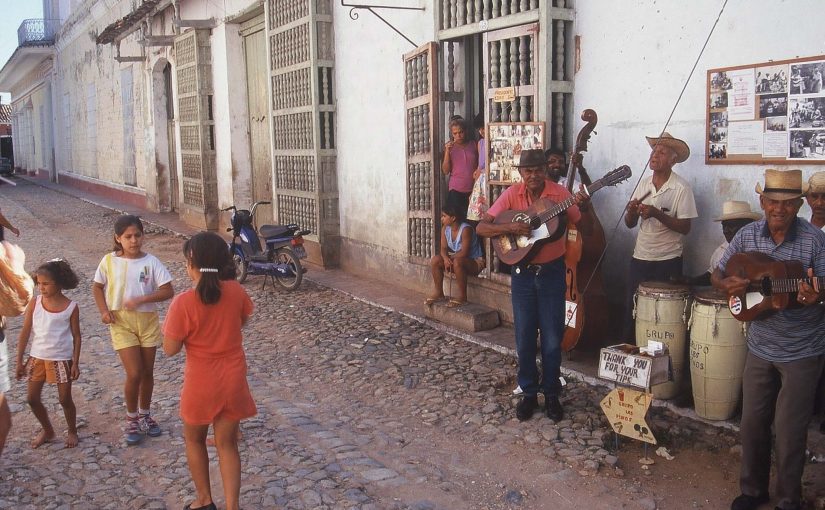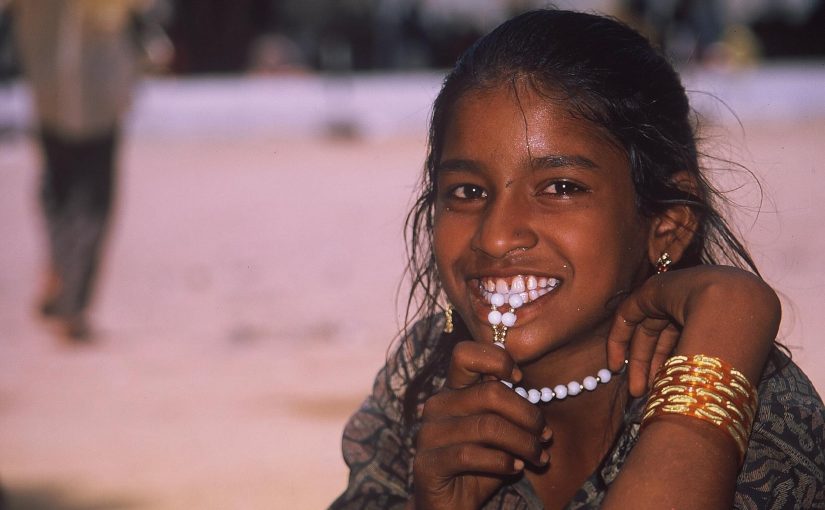オレの友達に、映画好きな奴がいた。
今日、オレは「プレッジ」という映画を観て来た。
定年を迎える刑事が、ある殺人事件を追っていく話だ。
とても切なく、やりきれない話だった。
誰のせいでもないのに、みんなが不幸になっていく話。
現実と似ている。
現実は、誰のせいでもないのに、みんなを不幸にしていく。
強すぎる愛情が、情熱が、そういうのを持っているその人自身を、どんどん不幸にさせていく。
オレは、そういうものだと思っている。
その友達は、ニューヨークへ行った。
学校を辞めて、ニューヨークへ行った。
オレの知らない間に。
いつの間にか行っていた。
そいつが。
オレと遊んでた頃。
よく飯を食いに行ったりしてた頃。
”この映画観てみろよ” ってオレに渡したその映画。
「インディアン・ランナー」という題名だった。
「プレッジ」と同じ監督が撮ったものだった。
ショーン・ペンという役者が撮った。
それは。
その映画は。
愛情の強すぎる兄弟が、愛情が強すぎるが故に相容れず、離ればなれになっていく悲しいお話。
うまくいかない人達の、悲しいお話。
不幸せな人達の、不幸せな物語。
でもオレは、それにでてくる人達が好きだった。
情熱を秘めてて、思い入れが強すぎて、破滅していく人達。
人を、あらゆるものを愛し過ぎるが故に、破滅していく悲しい人達。
弱さが、罪のないほんの少しの弱さが、人をおとしいれていく……
何だか、切なくて、やるせなくて、大声で叫び出したくなる。
何で、そういう純粋な人達が悲しい思いをしなくちゃならないんだろう?
どうしてそういう正直な人達が、辛い思いをしなくちゃならないんだろう?
そいつも、オレの友達も、思えばそんな奴だった。
ニューヨークに行ってからは消息不明で、ホームレスになっているという説もある。
ちょっと信じられないけど、あいつならあるかもな、と思ったりもする。
そのときはあんまり思わなかったけど、今ならあいつが「インディアン・ランナー」を好きだった理由も分かるような気がする。
悲しみを知っていたんだと思う。
人間の、どうすることもできない、終わらない悲しみを知っていたんではないかと思う。
不公平だ。この世の中は、公平ではない。
まじめな人が報われない。
純粋すぎる人達は、そうであるが故に辛い思いばかりする。
どうしてだろう? どうしてなんだろう?
誠実な人であればある程、不幸になる世の中だ。
もし神様がいるならば。
万能で、全能の、神がいるならば、一体どうしてこの世の中をこんなふうにつくったんだろう?
こんなにも不完全につくったんだろう?
それがみんなを苦しめる。みんなに辛い思いをさせている。
孤独で、ひとりぼっちの、悲しい世の中だ。
寂しい。とても寂しい。
ふと気が付くと、みんなの笑顔が思い出になって、自分だけが取り残されて、全ては過ぎ去った過去の海へと呑み込まれていく。
目が覚めると、家の中にひとりぼっちで誰もいなくって、とても静かで、この世界にたったひとりのような気がして、誰かに会いたくなって、話がしたくなって、落ち着きもなく右往左往する。
胸が掻きむしられるように痛くって、心細くって、とても不安で、誰かに抱き締めて欲しい。強く、しっかりと抱きしめて欲しい。
悲しみは、終わらない。寂しさは決して無くならないーーー
みんなの笑顔が、オレを苦しめる。
楽しかった思い出が、オレを苦しめる。
もう戻らないあの時間が、とても輝いてみえる。
インディアン・ランナーは、メッセンジャーとなって駆け抜けていった。
オレの心に何かを打ち込んで駆け抜けていった。
打ち込まれたそのものは、人間の悲しみの質量をオレに教える。
それは、打ち込まれた楔となって、いつまでもオレの心に残り続ける。