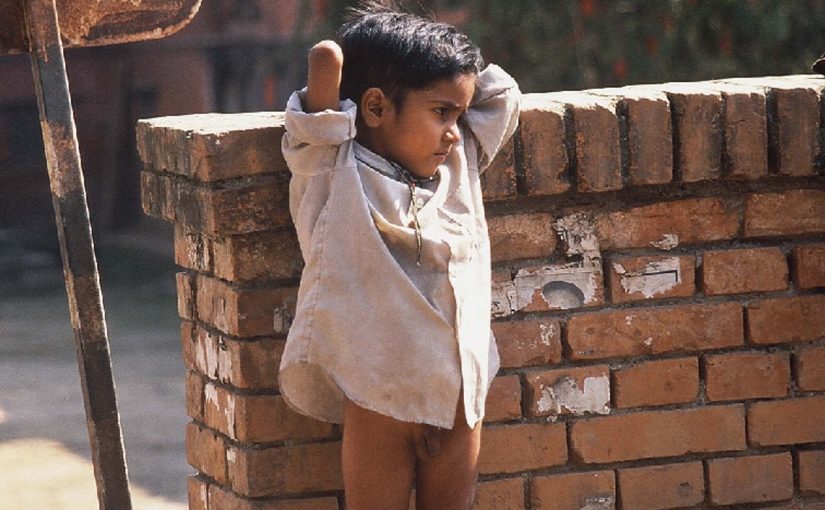「理見ちゃん、ヘロインってやったことある?」
「ヘロイン? そんなに何回もやったことはないけど、一応あるわよ。チベットでヒッチしてる途中にエベレストのベースキャンプでやったわ。一緒にいた人が持っててね。でも、確かに凄かったけどあんまり好きじゃないかな。あの感じ。ぐったりするし……。智はやったことあるの?」
「俺、プシュカルにいたときに、たまたまゴアで会った奴らと再会して、そのとき偶然手に入れたんだ。もっとも、手に入ったのはヘロインでなくってブラウンなんだけど。だから最近ちょくちょくやってるんだよ」
「プシュカルで? 良く手に入ったわね。インドではあんまりヘロインとかブラウンなんて見ないから。どう、どんな感じ?」
「俺は初めてだからそれがどれ程のものなのか良く分からないけど、そいつらは凄いって言ってたよ。俺も確かに凄いとは思うけど」
「それ、今持ってるの?」
意味ありげに理見は微笑んだ。
「うん」
「ちょっとやってみない?」
「いいけど、今日これからバスに乗るのに大丈夫?」
「大丈夫よ、そんなの。まだ大分時間あるし」
理見にそう言われて智はブラウンのパケットを取り出した。そして鏡を用意して、その上にラインを二本引いた。その間に理見は、既にルピー札を丸めてスニッフィングの準備をしている。智は、そっとその鏡を手渡した。瞳を輝かせながら理見はそれを受け取った。そして一息つくと、ゆっくりと鏡の上のラインを吸い込んでいった。一本分全て吸い込んでしまうと、彼女は、目を閉じて効き目の表れてくるのを待った。そして智も、ベッドの上に置かれた鏡を手に取ると、同じようにその上のラインを吸い込んだ。
マナリーのチャラスがキマッた頭に、ブラウンシュガーがダイレクトに響く。今までとは違った波が、後頭部の辺りから智を襲う。その変化に少し不安を感じながら智が何とか乗りこなそうとしていると、陶酔した理見の声が聞こえてきた。
「これ、いいわよ、智、凄い……、何かチャラスと似てるけど、全く違うものが中に入ってきてる感じ……。ああ、凄いわ……」
「ヘロインとは違う?」
「どっちかっていうとオピウムに近いわ、でも、オピウムよりも断然強烈よ」
理見は、ブラウンの感覚を確かめるかのように再び目を閉じた。顔の緊張が解け、表情が和らいでいくのが分かる。ブラウンシュガーのもたらす効果をじっくりと味わっているように見える。それは、子供のように無邪気で、なおかつ落ち着いた表情だった。きれいだな、と智は思った。美しい彫刻を見るような心持ちで理見を見つめた。見ていると、とても穏やかな気分になった。ブラウンシュガーがだんだんと効いてきて、体が沈み始める。全身は微熱を帯びている。理見は、ゆっくりと目を開けると、先程までとは違う緩やかな口調で智に言った。
「智、私、ここに横になっていい?」
「ああいいよ、ちょっと待って、その辺の物どかすから」
そう言って智は、ベッドの上に散らばっている自分の衣類を手早くまとめると、全て床の上へ放り投げた。理見は、ありがとう、と言うとベッドの上に横になった。とてもリラックスした表情で彼女は枕に顔を埋めた。智は、その様子を眺めながら床の上に座り込んだ。壁にもたれかかると、冷んやりとして気持ちが良かった。空気が乾燥しているので、陽の差さない部屋の中はそんなに暑いわけではない。