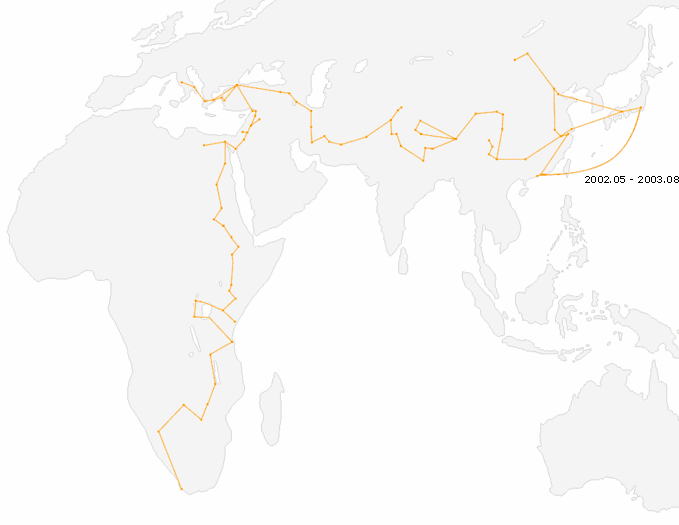私はその聖山をこの眼で見て、その道を歩いたことを忘れることはない。
この長い旅の中でも、最も過酷でそして最も心の動いた場所になるだろう。
ここでの経験がこれから先の日本での生活で、自分を助けてくれる。
それは確信に近い。
日本での困難と、カイラスとは何の関係もないが、そんな気がしてならない。
巡礼者が五体投地をしている。
「タシデレ」と挨拶の言葉をかけ、カメラを向けると
『どこから来た?』と返してくれる。
『日本からです』と答えると、それはいいと言わんばかりの笑顔が灯る。
身にまとった民族衣装の上には服を守るための分厚いエプロンのようなものを付けている。
手にも、保護のため分厚い手袋をはめている。
どちらも埃にまみれ、ところどころ穴があいている。
それを見ると、五体投地の壮絶さが伝わってくる。
しかしその壮絶さとは裏腹に、表情はやわらかい。
チベット人の誰もが一度は訪れたいと思うカイラス。
ヒッチハイクの途中でチベット人にカイラスに行くと言うと誰もが喜んでくれた。
『がんばれ、しっかりやれ』
とでも言われた気がする。
もちろんそんなチベット語は知らないが、そんが気がしてならない。
そして私も憧れ続けたカイラスにとうとう来た。
『ここに来るまでにいったいどれだけの月日がかかっただろう』と改めて思う。
もちろんラサからの日数でも、日本からの日数でもない。
その聖山を知ってから、ここに辿り着くまでの月日である。
もともとその聖山のことを知ったのは、おそらく数年前のNHKのTVの特番だったと思う。
ある巡礼者に焦点を当て、彼らがラサからカイラスまでを五体投地で巡礼する様を追った内容だったと記憶している。
当時、ラサにさえ行ったことのなかった私は、西チベットの広大な風景に憧れ、巡礼者の壮絶な姿に驚き、カイラスの神秘性に魅せられてしまった。
しかし交通機関の未発達な西チベットは、旅行者の簡単に行ける場所ではないし、何より標高5000mを超えるその巡礼路は実現不可能な夢に思えた。
カイラスは一度は私の中で風化していったが、この旅でラサへ行くことを決め、チベットの情報を集めているうちに再び浮上してきた。
しかしわからないことだらけで、富士山も登ったことのない私にとっては、
5000mを超えること自体未知の世界だった。
期待より不安の方が強かったがラサまで行けば、なんとかなるだろうと腹をくくって、行くことを決心した。
そのためにテント、ガソリンコンロ、防寒具などを用意し、準備万端でそこを目指した。
トラックをヒッチハイクして、他の見所もいくつか見た後、カイラスの基点となる
街、タルチェンに着いたときには、ラサを出てからもう1ヶ月たっていた。
その街から丸1日歩きカイラス北面に着いた。
標高はすでに5000mを超えている。
心配していた高山病は、既に高地順応がすんでいるのでなんともない。
しかし空気が薄いことは、少し歩いただけで体全体で感じる。
いくら空気を吸っても、空気が足りない。
そこでテントを張り1泊したが、寒さは想像を超えていた。
夜はダウンジャケットを着て寝袋に入って寝たが、寒さのあまりなかなか寝付けない。
眠ったと思っても、寒くてすぐに目が覚めてしまう。
朝方にはテントのなかに入れておいた水筒の水も凍り、テントそのものも凍っていた。
テントを出て、靴に足を入れると、靴の冷たさで足が痛い。
日が昇り北面に日が当たり始める。
空は考えられないほど澄んでいる。
雲はもう手が届きそうなほど低い。
カイラスは自分の目の前だ。
雪に太陽が反射して、カイラスはその存在感を増す。
荘厳なその姿は、美しいという言葉だけではとても表現できない。
そのに神が住んでいると言われても、私はなんの疑問も持たないだろう。
私は言葉さえなく、シャッターを切った。
何枚も、何枚も・・・
その日の午後から再び歩き出し、ドルマ・ラを超えた。
そこは5668mと巡礼路のなかで最も高い。
もちろん私の人生の中でも最も標高の高いところだ。
あたりは雪で覆われていて、時折膝のところまで足がはまってしまう。
無数のタルチョ(経典の書かれた旗)がはためき、それが風になびいている。
風は冷たいというより、痛いくらいだ。
私の心臓はもう限界といわんばかりに、バクバクと最速の鼓動を繰り返している。