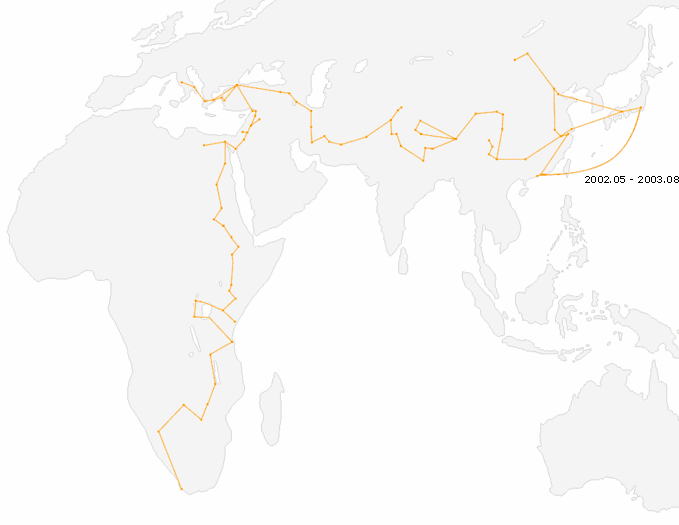事の始まりは、ウマイヤドモスクの前だった。
私がそこを歩いているときに、ある男二人組みに声を掛けられた。
『ウエルカム ジャパニーズ 腹は減ってないか?』
と、あまりに唐突に聞いてきた。
『今、食事したばかりだ』
と言うと、
『だったらチャーイを飲みに家にこないか』
と誘ってきた。
男の一人は30歳くらいの髭のおとこで、彼は英語ができなくて、ただいつもニコニコとしていた。
そして、もう一人の年配の50歳くらいの男が、多少の英語ができて、私に話し掛けてきた。
彼は小柄であり、親しみの持てる顔だった。
名前は恐ろしく覚えにくく、私は勝手にアブドルと呼んでいた。
彼らの突然の誘いには驚いたが、私は、彼らを信頼した。
また、別に何かに巻き込まれても、それはそれで構わないという投げやりな気持ちもあって、そこから歩いて5分という彼らの家に行く事にした。
確かに5分ほどで彼らの家に着いたが、あまりに入り組んでいて、とうてい一人では引き返せそうにない場所にあった。
2階建ての建物のなかは、以外に清潔だった。
玄関もトイレも下手な安宿よりはよっぽど清潔だ。
通された8畳ほどの部屋には、アブドルの姪だという、3人の10代後半の女性がいたが、すぐにアブドルに追い出された。
彼女らは明らかに、私に好奇の視線を向けて、興味津々であったが、仕方なく部屋から出ていって、庭の窓からこちらを覗いていたが、さらにアブドルに追い払われた。
私としては、彼女らも一緒にいたほうが楽しいと思ったが、やはりイスラム教の教義上あまりよくないのかもしれない。
部屋の外観はきれいであったが、室内は雑誌やら、食べかすやらで散らかっていて、さらに彼女らが吸ったたばこの吸殻もたくさんあった。
彼女らは、通常のイスラムの女性が髪を隠すためのスカーフもしていなくて、あんまり行儀の良いタイプではないのかもしれない。
とにかく、女性陣を追い出してから、散らかった部屋を片づけて、でっかいタンクと一体式のコンロでお湯を沸かして、甘いチャイをつくってくれた。
アブドルは英語からアラビア語の翻訳の仕事をしていると言うわりには、英語は苦手なようであった。
読むのならできると言っていたが、発音は驚く程たどたどしい。
そしてアフドルとチャイを飲みながらしばらく他愛のない話をした。
旅の話や、家族の話などである。
それ以上の話は、お互いの英語力では無理だった。
その時も、髭の男はニコニコと笑っているだけだった。
お互いに会話に詰まり少し間ができた後、アブドルは突然、ベッドの脇にあった、髭剃りを取り出して、それを私にくれると言った。
メモリーだそうだ。
そして、部屋を見渡して、部屋の隅からろうそくを見つけると、4本を取り出して、私の前に持ち出した。
4本あるのは、私の父と母と兄と、私のためだと言う。
さらに、ベッドの脇にある、プラスティックでできた絨毯のゴミ取り用のローラーも、ぜひ持って行ってくれと私の前に置いた。
髭剃りは、まあ、使えないこともない。
ろうそくは果たして、自分の家族が喜ぶかどうかは別として、これからアフリカで使うかも知れない。
ただ、絨毯のゴミ取りは、どう考えても旅には必要ないし、日本まで持って帰ったとしても、ゴミ取りとしての効果があるとは思えなかった。
私は、髭剃りとロウソクは頂くが、ゴミ取りはアブドル必要だろうと言って断った。
しかし、ガンとして彼は引き下がらなくて、私はしぶしぶ、いや、表情はありがたく、もらうことにした。
ちなみに、髭剃りは1回使っただけで壊れ、ゴミ取りは持ち歩くのがどうしても邪魔で、申し訳ないとは思ったが、ダマスカスの安宿においてきた。
ロウソクだけは持ち歩いている。
アブドルは、この後どうしたいんだと言うので、私は以前から行きたかったハマムに連れて行ってもらうことにした。
ハマムとは、トルコ式の公衆浴場のことである。
私はイスタンブールに長くいたくせに、まだ一度も行っていない。
しかしアラブ諸国ならどこにでもある。
だからダマスカスで行ってみようと思っていた。
しかもガイドブックに載っているようなところではなく、地元の人しか行かないような所に行ってみたかった。
アブドルは快く私の申し出を引き受けてくれた。
彼の家を出て、また、どこをどう歩いたかはわからないが、5分ほど歩き、スークの一角にあるハマムへと連れていったもらった。
入り口を入ると、大きなスペースが広がっていて、腰掛けるところがあり、着替えをしたり、くつろいだりできるようになっていた。
そのハマムは、垢すりとマッサージを入れて200シリアポンド(約4ドル)だった。
私はそこでアブドルと髭の男と別れた。
アブドルも一緒にハマムに入ろうかと言ってくれたが、余計な金を使わせても悪いので、一人で大丈夫だからと言って帰ってもらった。
最初、彼らの唐突な誘いに、胡散臭いものを感じはしたが、結局は親切な人たちであった。
私は丁寧にお礼を言って別れた。
さてと、と思い、私は準備をした。
このハマムというやつには、かなり期待していた。
それは、面白いほど垢が落ちると聞き、イスタンブールでも行こうかとは思ったが、結局のところ行っていない。
だから、このダマスカスでは絶対に行くと決めていた。
まず、私は服を全てぬぎ、腰のところに布をまいた。
これが入浴のスタイルだ。
そして、従業員が浴場まで案内してくれた。
そのときに、私は、
『垢すりとマッサージを頼む』
と念を押して頼んだ。
英語で伝わらないから、ゼスチャーで伝えた。
そして、その従業員も、わかったわかったと肯いて、これで大丈夫だろうと思った。
浴場と言っても、日本のそれのように、湯船があるわけではない。
体を暖めるサウナの式の浴場と、その他に、体を洗うための小さい部屋がいくつかある。
その部屋には、ドアなどはないが、部屋は入口から横へと広がっていて、ちょっと外から見ると、目隠しみたいに部屋の内部は見えないようになっている。
私は、トルコ風呂のは入り方というのを、その時知らなかった。
本当なら、まずはサウナで温まり、そのうちに垢すり師なり、マッサージ師なりが入ってくるので、彼らにやってもらうのである。
それを知らない私は、サウナに行っても、垢すり師が来ないので、他の客に聞いてみた。
それが間違いだった。
何人かは、私の言っていることがよくわからないという表情であったが、そのうちの一人が、
『俺がやる』
と確かに言った。
その40歳くらいの痩せた男は、
『ベトナム人か』
と私に聞き、
『いや、日本人だ』
と私がこたえると、ニヤリとした。
私はやっと、垢すりにありつけると思い、彼に連れられて、個室へと連れていかれた。
そこで、
『うつ伏せになって、布をとれ』
と彼は言った。
そこの個室だけは、電気が消えていて、薄暗かったが、それは垢すりを受ける客への配慮なのだろうと、その時は思った。
しかし実際には、その垢すりの彼がわざと消していたとすぐにわかることになる。
彼は石鹸をもって、私の背中につけ、タオルで洗いはじめた。
それは妙に、優しい洗い方だった。
もっとごしごし洗うと聞いていたので意外だった。
そんな洗いかたで、はたして垢が落ちるのだろうか、そんな事を思った。
そして数分して、彼の手が、「そこは自分で洗えるから結構だ」というところに伸びてきた。
私は、びくっとして起き上がり、
『そこは必要ない』
と言った。
この時から私は、彼に対してある種の疑惑を持ちはじめたが、
『彼はプロなのだ』
と思い込んだ。
プロの彼に対して、こちらが妙に恥ずかしがっては、彼の仕事にならない。
そんなふうに思った。
彼はまた私の背中を洗い始めた。
その洗い方はさっきと同じで、とても垢が落ちそうではなく、やたらとなめらかだった。
すると彼は、次に私の背中に乗り、なにやら体を揺すり始めた。
それは私の背中を洗う手と連動しているので、さほど不自然ではないが、どうもおかしい。
私は、またしてもがばっと、彼を跳ね除けて起き上がり、
『お前、ホモじゃないのか』
と私は言った。
彼は、その英語が理解できないようで、きょとんとしていた。
そして、また寝ろと言う。
『いや、彼はプロなのだ。
垢すりのプロなのだ。
彼特有のやり方というのがあるのだろう』
と私は思った。
そして再びうつ伏せになると、彼はまた背中を洗い始めた。
そしてしばらくして、再び彼は私の上に乗ってきて、手と同時に体を揺らし始めた。
そして、その時に、はっきりと、私の肌は、ある異物の感触を感じたのである。
私は彼がすっ飛んでいくほどの勢いで跳ね起きて、日本語で彼をまくしたてた。
『お前はやっぱりホモか。
いや絶対にそうだ。
そのお前のその、目の前のものがその証拠だ。
いや、別に俺はホモを否定する気はない。
でも、ホモだってゲイだって、誰とでも寝るわけじゃないだろう。
彼らにだって、恋愛感情ってやつがあるだろう。
お前にはそれがないのか』
もちろん私は日本語なので、彼には理解できない。
彼は、再びきょとんとして、
『なんだ、お前は違うのか・・・』
みたいな顔をしていた。
私はすぐにそこを出て、他の誰もいない部屋へと行き体を洗った。
そして、脱衣所までもどり、バスタオルを乱暴にふんだくって、さっさと服を着た。
その様子をおかしいと思った従業員が集まってきて、
『どうしたんだ、はやすぎるじゃないか』
と聞いてきてくれたが、英語で説明しても全く通じない。
なので、なんとかゼスチャーで、ホモに襲われたと説明すると、全員がどっと笑った。
それを見て
『他人事だと思いやがって』
と私は、二重に腹がたってきた。
ただ、年配の従業員の一人が、
『そいつは誰だ?案内してくれ』
と言ってくれたが、私はもう、奴の顔も見たくなくて、早くそこから出たかった。
しかし、当然金だけは請求される。
『いいか、俺は被害者だ。なんで襲われた上に、金まで取れなくてはいけないんだ』
と言っても通じない。
そこでまたもめるのも嫌なので、マッサージ代は払わず、入浴代だけをおいて、さっさと店をでることにした。
もう、つまらないことで、もめて、そこに居るのが嫌だった。
一刻もはやく、そこを出たかったのだ。
茫然と夜の旧市街を歩いていると、偶然にアブドルに会った。
『どうしたんだ?やけに早いじゃないか』
と言う彼に、事のなりゆきを話すと、彼は心から申し分けなさそうに、
『ソーリー、ソーリー』
と何十回となく、連発していた。
『よかったら、気分をなおして、夕食を食べにこないか』
と誘ってくれたが、
『いや、もうホテルに帰りたい』
と言って断った。
すると、彼はポケットの中から小銭をかき集め、私に渡そうとした。
それは、50シリアポンドで、約1ドルの額だった。
その顔は全ての責任は私にあるとでも言っているかのようだった。
私は、
『あなたに責任はないし、そんな事をする必要もない』
と言って断った。
最後にアブドルは、
『シリアのことを嫌いにならないで欲しい』
と言っていた。
私は一人で歩きながら、やはりこの街を嫌いになることはないと思った。
黄色い明かりに浮き出された古い街並みはやはり美しかった。