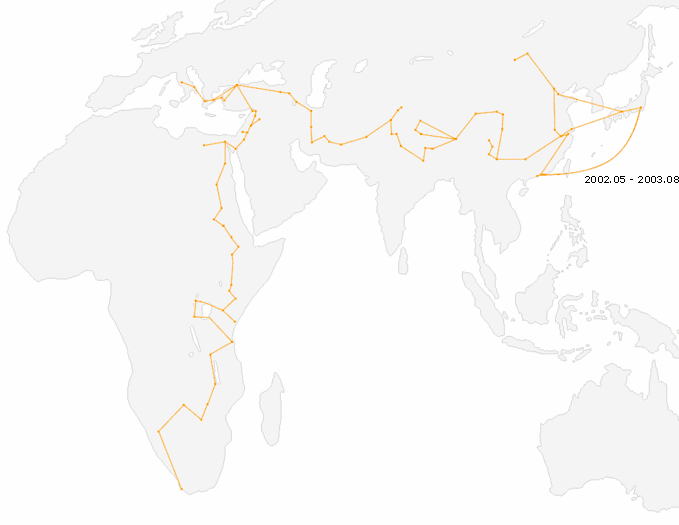ギリシャへは船で入った。
セルチュクから、今まで来た道を少し戻るようにイズミールまで行き、そこでバスを乗り換えチェシメという港街まで行った。
初めて見るエーゲ海の水はエメラドグリーンだった。
きっと今が夏で、雲ひとつない空だったらもっと、気分も晴れただろう。
でも、空には青一つ見えなくて、ときおり青空が顔を覗かせた思った途端に雨が降っふったりする。
それでも海は濁らないで美しい。
なぜだかそれは残酷だ。
それは一方が変わり続けるのに、もう一方が変わらないからかもしれない。
そこで1泊し、そこから1時間ほど高速船に揺られ、ギリシャのヒオス島に着いた。
たったの1時間しか乗らないのに40ドルもかかり、納得のいかない料金だったが、どうもボラれたわけではないようだった。
そのヒオス島で半日ほど時間をつぶし、その夜アテネ近くの港街、ピレウス行きのフェリーに乗った。
こちらは一晩揺られても22ユーロ(約2800円)だった。
ピレウスはアテネからバスで30分ほどのところにある街だが、すぐにアテネに行くことをやめ、そこで1泊することにした。
港から15分ほど歩いて目的の宿に着き、3時間ほど眠りについた。
昨日のフェリーのシートで、眠れなかったわけではないが、やはり移動が続いて疲れていた。
目を覚ますと、エミもまだベッドにいた。
しかしやはり目を覚ましていた。
だいぶ前に起きて、二人分のサンドイッチを買ってきてくれていた。
そのあと、再びベッドに入ったようだ。
私がそのサンドイッチを食べ始めると
『私、熱があるかもしれない』
とエミが言う。
額と首に手をあてると、たしかに熱い。
そのあつさは、尋常ではないものだった。
私はバックパックの奥から体温計を引っ張り出し、彼女に渡した。
そして、5分ほどして彼女からそれを受け取ると、その目盛りが39度を超えていたことに、慌てた。
これは病院に連れて行ったほうがいいかもしれない。
そう考えた。
しかしエミは
『大丈夫。私は熱に強いから』
と言って、薬を飲んで寝るという。
確かに、友人の看護婦から餞別にもらった薬を飲むその様子は、とても39度以上の熱がある病人には見えなかった。
とにかく様子を見ることにして、一日彼女は眠った。
フェリーのなかには、たくさんの人がいて、すなわちたくさんの菌がその空間に存在するわけだから、それで風邪を移されたのかもしれない。
夜には携帯用のガソリンコンロでお粥をつくり、それをエミに食べさせた。
そしてエミは薬を飲んで再び眠りについた。
次の日、熱は37度まで下がった。
きっと薬が効いたのだろう。
まだ安静にしていた方がいいことは、わかっていたが、私たちはアテネに移動した。
もし、病院に行くことになれば、ピレウスよりも、やはりアテネにいたほうがいいだろうと考えたからだ。
アテネ行きの市バスのなかで、エミは以外なほど元気だった。
やっと憧れの地に来たという思いもあったのかもしれない。
バスに乗るのは簡単だったが、目的のシンタグマ広場に行くのはどこで降りたらいいかわからなかった。
まわりの人に聞いたりしたが、英語が通じない。
困っていると、結局終点がシンタグマ広場だった。
そして、安宿には変わりないが、エミの体調を考え、トイレとシャワーの付いた部屋にチェックインした。
その日、
『ずっとホテルにいても気が滅入る』
という彼女を連れて、アテネの街を歩いてみた。
もうそこは完璧なヨーロッパだった。
まずそれを感じたのは若い女性のファッションだった。
体の線が出るジーンズをはき、ヒールやブーツで歩いている。
それは洗練されていると感じた。
物価もトルコとは比べ物にならないくらい高い。
そして何よりヨーロッパを感じるのは、そこに暮らす人たちだった。
カメラをぶらさげて歩いて、観光客だって一目でわかっても、アジアのような客引きや、あるいは何かを企んでいる輩や、ただ暇で興味があって話し掛ける、そういう人に話し掛けられることはまずなかった。
それは冬季という理由もあるのだろうが、それにしても少ない。
もちろん一人もいなかったわけではないが、そこにはアジアのような強引さも、陽気さも感じられなかった。
みんな、日本人なんか見慣れているかのようだった。
もちろん、別に彼らが冷たいわけではない。
こちらから何かをたずねれば親切に教えてくれる。
しかし彼らから話し掛けてくることが、今まで私の通過した地域と比べるとはるかに少ない。
そういう輩の多かった時には、それで疲れることもないではないかったが、ここに来ると何故かそれが懐かしく、そして今の状況が少し寂しく感じる。
それはきっとわがままな話だろうが、そう思った。
とにかく、もう、そういう地域に入ったのだ。
シンタグマ広場の近くに、無名戦士の碑というのがある。
そこには微動だにしない二人の衛兵がそれを守っている。
その前がちょっとした広場になっていて、軽く100羽をこえるハトが群れていた。
そこへ行くと、ハトの餌をビニールに入れて持ち歩いているおじさんが寄ってきて、
『餌はいらないか?』
と言う。
ただだという。
てっきり観光客にハトの餌を売るのが商売だと思っていたので、なんとなく不思議な思いで手のひらにそれをもらう。
すると、あっというまにハトが飛んできて、腕や肩、頭にまでハトがとまり、餌をつまんでいく。
それは、ハトがかわいいと思う感情を通り越して、少し恐かった。
するとその中年のおじさんは、今度はインスタントカメラを取り出し、
『写真はどうだ?』
と言う。
なるほど、ハトに囲まれたその様子を写真に撮って渡す。
それが商売なのだ。
私たちは、それがいくらなのかは聞かなかったが、写真はことわった。
その近くに大きな公園があり、エミの具合もだいぶ良さそうなので、そのまま行ってみることにした。
それはちょっとした森林公園になっていた。
小さな動物園と言っていいのかどうかわからないようなそれがあり、いくつかの鳥が檻のなかにいた。
孔雀が羽を広げて求愛している。
他にも蛍光色の名前のわからない、おそらくは南国の鳥が何種類かいた。
しかし、寒さのせいか、あまり元気ではない。
冬の動物園はどこか悲しい。
近くに池があり、そこにはアヒルが泳いでいる。
老女がパンを投げると、そこにはアヒルの群れができる。
そのパンを取ることができるのは、たった一羽のアヒルで、そのパンを取ったアヒルはそれを一気に飲み込むことができないらしく、まずは口にくわえたまま、ひょこひょこと走って逃げる。
でないとほかのアヒルが、そのアヒルの口もとからパンを奪ってしまうのだ。
少し離れたところで周りの安全を確かめてからアヒルはそれを食べる。
そして別のところではまた老女の投げたパンをめぐって、アヒルが群れていた。
私は老女を見ていた。
60歳くらいだろうか。
きっと娘や息子たちはとっくに巣立って、今は自分の時間を楽しんでいる。
パン屋で、前日に焼いたいらないパンをもらい、そこに毎日足を運んで、アヒルにパンをやるのが日課であり、彼女の楽しみだ。
そんなことを無責任に想像した。
老女は私に気づいたので、軽く会釈をし、老女もまたにっこり笑った。
私は、
『写真を撮らせてほしい』
ということを身振り手振りで伝えたが、
『それはだめよ』
と笑いながら答えてくれた。
そして、私たちほうへ近づいてきて、
『あとはあなたたちでやってね』
と言って、残りのパンを手渡して消えていった。
私とエミはそれを受け取り、パンを投げた。
遠くに投げなかったのがいけなかったのだろうか。
あるいは、ビニールのなかからパンを出し、それをアヒルに見せてしまったのがいけなかったのだろうか。
池に棲息するすべてのアヒルが、と書けば少々大げさかもしれないが、私たちはアヒルの大群に囲まれてしまった。
アヒルの足は池から上がり濡れていて、そこに泥がついている。
それが私とエミのズボンの裾や靴に見事について、それでもアヒルはパンを求め、私たちの膝や手をつついてくる。
私たちは泥だらけになってしまった。
宿に帰る道でエミは、
『ひどいことになっちゃったね』
と言った。
でもそれは決してひどい目に合ったような口ぶりではなく、やたらと楽しそうだった。
アテネはエミにとって憧れの地だった。
大学の卒業旅行でアテネに行こうとしたが、航空券のあまりの高さに断念したらしい。
かつては建築の道を志望していたので、ギリシャの古代建築や遺跡に興味を持っていた。
エミの体が回復してから、パルテノン神殿で有名なアクロポリスの丘や、いくつかの博物館や遺跡を一緒に歩いた。
エミはたんねんにそれを見てまわり、それなりには満足したようだった。
しかし、
『期待が大きすぎた』
とも話していた。
それに遺跡はともかく、街そのものはあんまり好きにはなれないとも言っていた。
何より季節が悪かった。
日本と同じくらい寒くて、雨も多かった。
それはいつ雪に変わってもおかしくないくらいだった。
いっそのこと、意地悪く降る雨よりは、雪になったほうがまだいいのにと思った。
アクロポリスに行った日も雨だった。
またエミが楽しみにしていた、国立考古学博物館が、改装工事中で閉館していたのもその理由の一つかもしれない。
私はといえば、遺跡や博物館よりも、エミと一緒にハトやアヒルに囲まれ、『ひどいことになっちゃったね』と笑いながら話したことの方が、記憶の中で、遥かにいきいきと生き続けている。
私はこのアテネで30歳を迎えた。
10年前は自分が30歳になることなど考えたこともなかった。
それはいつ訪れるかもわからない、遠い未来で、まるで他人事だった。
5年前は30歳までにはという思いがあった。
『30歳までにはもう一度旅をしたい』
そう思っていた。
その思いは何度も自分の中でかき消されては、またどこからか降ってわいたように現れて、ときには忘れていたが、やはり常に心のどこかには確実に存在していた。
そしてこれが最後のチャンスだと、これが最後の旅だと決め、旅に出た。
それは夢が叶った、希望が実現したともいえる。
しかし1年前、エミと婚約したときには、こんな気持ちで誕生日を迎えるなんて、考えてもいなかった。
今、自分にとって、旅というものが一体どれほどの価値があるのかと考えてしまう。
少なくとも、将来を一緒に過ごすと決めた人を置き去りにしてまで、するほどの意味があったのだろうかと。
いや、うまくいっていればそんなことは考えなかっただろう。
勝手なものだ。
誕生日の夜、友人から何通かメールがあった。
旅先にいると、そうした日本との繋がりはなおさらありがたく感じる。
その中に私とエミの微妙な関係を知った、旅先で会った友人からのメールがあった。
今まで私は、日本で待つ側と、旅に行く側の時間の流れ方の違いしか考えたことがなかった。
エミは今までと同じように仕事をこなし、時には友人と遊び、同じような事を繰り返す日常のなかで8ヶ月を待っていた。
しかし私は、やはり日本の生活と比べれば、刺激にあふれて、いきいきとした8ヶ月を過ごした。
それはきっと時間の感じ方というのが違う。
しかし彼のメールは、私の選んだことのその意味を、もっと深く考えるきっかけを与えてくれた。
それは彼女に「1人で待っていて欲しい」ということと、彼女が私に「旅に行かないでくれ」と求めることは同じ意味なのではないかというものだった。
つまり、私が何年も前から考え、憧れたつづけた旅というものを、諦めることと同じくらいのつらさを、彼女は味わったのではないかと。
もし旅を諦めたら、自分はどうなっていただろうか。
やはり苦しんだろう。
そして、やがてそれはエミをも苦しめることになっただろう。
私はそのメールを読み、何か、取り返しのつかないことをしてしまったのかもしれないという思いにかられた。
別にそのメールは私を責めるものではなかった。
私はそのメールで救われたと思った。
彼のその言葉で、自分の選択したことの意味を正確に理解できたと思った。
そして、日本に残されたエミがどんなふうに8ヶ月を過ごしたか、わかる気がした。
エミは2月11日のイスタンブールから成田のチケットで帰国するだろう。
そのことはすでにわかってしまった。
私が30歳を迎えた後、正確にいつかはわからないが、エミは、
『私、多分、帰る』
と言った。
それはもう、私にはどうにもできないことだった。
エミにとっての憧れの地に来ても、やはり何も起こらなかった。
人の気持ちなんて、どうやったって自由になるものではない。
しかし、私自身の気持ちもエミには届いたはずだった。
その上での、彼女の答えだった。
しかし飛行機の日までは、まだ時間はある。
私たちはアテネの街で時間を持て余していた。
遺跡や博物館を一通り見てしまうと、もうやることがなかった。
別にただあてもなく、街を歩いても、何か面白いことが起きるでもなく、ただ寒さに体を丸くするだけだった。
それは私にとっては、ただ寒いというよりは、街を歩けば何かが起こる地域から、そうではない地域に入ったということを肌で感じるものだった。
はやくこの街から出たいと思っていた。
もうどこでもよかった。
ただ、エミと最後の時間を笑顔で過ごせるところに行きたかった。
それが最後の望みだった。
『イタリアでジェラートを食べる』
私たちはそんなどうしようもなくくだらない理由で、イタリアに行くことにした。
でもそんなふうに旅をするのは魅力的だった。
ローマで最後の時を過ごし、そしてローマで別れるというのも悪くはない。
私はそんなふうに考えていた。